Job総研が2025年に行った調査によると、現職場でストレスを感じている割合は全体の76.2%に及ぶそうです。
働き方や人間関係でストレスを感じている人が多く、相談できる人が身近にいないことが原因の一つと考えられます。
建設業でも、トップダウン型の経営体制や指導が厳しいことで知らない間に職場でストレスを感じる人が増えている可能性があります。
ここでメンタルヘルスケアの重要性と対策方法を把握して、予防しましょう!
メンタルヘルスケアとは

メンタルヘルスは「心の健康状態」のことをいいます。
メンタルヘルスケアは、心の健康を保つための取り組み全般を指します。
職場でいえば、ストレスを感じにくい環境づくりや、悩みを抱えた社員が相談しやすい体制作りのことです。
「疲れている」「眠れない」「やる気が出ない」といった小さな不調に気づき、早めに対処することで、うつ病などの深刻な状態を防ぐことができます。
最近では、社員の離職防止や生産性の維持という面からも、企業にとって欠かせない施策となりつつあります。
精神的な病は身体的なものより治りにくいと言われているので、従業員のメンタルに不調が来る前に対策をする必要があるのです。
メンタルヘルスに影響を及ぼす要因
 メンタルヘルスに悪影響を及ぼす要因は、一つではありません。
メンタルヘルスに悪影響を及ぼす要因は、一つではありません。
どんなことがメンタルヘルスに影響を与えるのか知っていきましょう。
長時間労働
長時間労働は、従業員の元気やプライベートな時間を奪い、働く理由を奪っていきます。
生活を安定させるため、充実させるために働いているはずなのに、長時間労働のせいでプライベートを楽しむ時間も活力もなくなってしまいます。
そうなると、何のために働いているのか分からなくなり、精神的ストレスを強く感じるようになります。
定時をとっくに過ぎているのに帰れない、仕事が終わらないというのも大きなストレスになります。
建設業では、人手不足が大きな課題であり、長時間労働を解消できない企業も多いでしょう。
そういった職場環境が根付いていると、従業員のストレスや不満も大きくなってしまいます。
人間関係
人間関係による精神的ストレスは、どんな職場でも起こり得ます。
職場にはいろんな人がいるので、全員と気が合うことはないというのは誰でも理解しているでしょう。
しかし、直属の上司や同僚など、仕事で関わる頻度が高い人とあまりにも相性が悪いと、毎日がストレスになってしまいます。
建設現場では親方の指示に従うことが多いので、親方の指導が厳しかったり職人気質で人当たりが強かったりすると、それに従う従業員がストレスを強く感じてしまいます。
周囲の人とのコミュニケーションがうまくいっていないと、相談しにくい環境が作り上げられ作業効率も落ちてしまいます。
人間関係は離職理由に直結するものなので、問題があるなら今すぐに改善を進めましょう。
職場環境
駅からのアクセスが悪い、職場の広さ、騒音、空調、ITツールの使いにくさ、働き方が選べないなどの職場環境にもストレスを感じやすいです。
駅から歩くとなると、その分早めに出勤する必要がありますし、気温や天気に影響を受ける時間が長くなります。
また、テレワークなど働き方の自由がないと、万が一に備えられず対応の悪さに不満を感じやすいです。
もしアナログな職場環境が固定化されているようなら、改善を試みるのがおすすめです。
責任の大きさ
ノルマがあったり、自分の役職に対して仕事の責任が重すぎたりすると、背負いきれずに精神的ストレスを感じてしまいます。
ノルマは目標値として必要だとは思いますが、「必ず達成しないと減給」などの厳しすぎる条件があると、従業員は必ず達成しなければというプレッシャーで大きなストレスを感じます。
責任が重すぎる場合も同様で、失敗してはいけないというプレッシャーで精神的に追い詰められてしまう可能性があります。
ノルマも大きな仕事も、その人の能力やキャパシティに合ったレベルで与えるようにしましょう。
私的要因
例えば、介護や育児など、職場以外の要因で疲れがたまり、それに職場環境のストレスが重なることで精神的にきつくなることがあります。
これは仕事の様子を見ているだけではなかなか判断しにくいので、しっかり話を聞く時間を設ける必要があります。
私的要因だけではそこまでストレスを感じなくても、そこに職場や仕事のストレスが加わることで、取り返しのつかない精神的ストレスに変わる可能性があるので注意が必要です。
メンタルが弱るとどうなる?

メンタルが弱ると、心だけでなく体や行動にもさまざまな変化が現れます。
たとえば、以下のような症状が出てきます。
- 何をしても楽しく感じられない
- イライラや不安が強くなる
- 気分の浮き沈みが激しくなる
- 自分を責めてしまう
- 考えすぎて眠れなくなる
- 人と話すのが億劫になる
- 仕事や家事のミスが増える
- 疲れやすくなる
- 仕事のことを考えると気分が悪くなる
このように、感情面だけでなく行動にも影響が出ます。
健康に働き続けるためにも、上記のような症状が出たら一度心と体を休める時間を取りましょう。
有休をとって好きな場所にいく、温泉などリラックスできる場所にいく、おいしいものをたくさん食べる、など、あなたの好きなことをする時間を取りましょう。
従業員が好きな時に休息を取れるように、会社側は環境を整えておく必要があります。
代表的な精神疾患
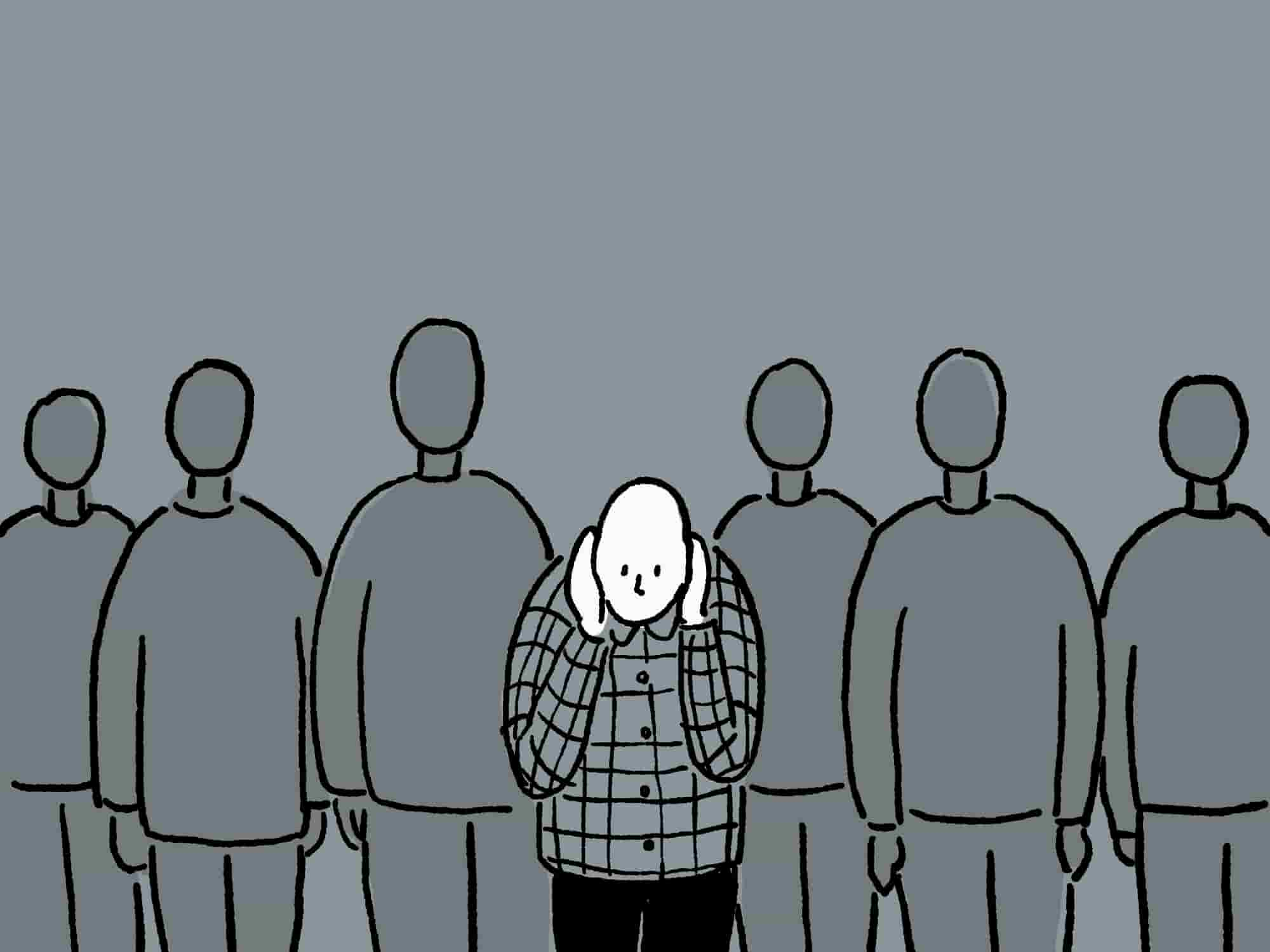
ここで、代表的な精神疾患を紹介します。
どういった症状なのか知って、このような事態にならないように会社側で対策をしてください。
うつ病
うつ病とは、強い憂うつ感や無気力な状態が長期間続く心の病気です。
誰にでも気分が落ち込む日はありますが、うつ病の場合は「眠れない」「食欲がない」「何をしても楽しくない」といった状態が2週間以上続き、日常生活に支障が出るのが特徴です。
うつ病では、脳が正常に働かなくなっているため、考え方やものの見方が否定的になります。
原因は過度なストレスや環境の変化、性格傾向、脳内の働きの変化などさまざまです。
真面目で責任感が強い人ほど発症しやすい傾向もあります。
自分を責めたり、周囲との関わりを避けるようになったりすることもあり、早期発見・早期対応がとても重要です。
うつ病は「心の甘え」ではなく、治療が必要な病気です。
適切な休養や医療的支援を受ければ、回復することができます。
うつ病と誤解されがちな病気として「双極性障害」があります。
双極性障害は、気分が高揚する躁状態と、気分が沈むうつ状態が繰り返される病気です。
以前は「躁うつ病」といってうつ病と同一視されていましたが、今は別の病気として認識されており、治療方法が異なるため、うつ病か双極性障害かの診断はとても重要なものです。
パニック障害
パニック障害とは、突然理由もなく激しい動悸や息苦しさ、めまい、発汗、震えなどの発作(パニック発作)に襲われる病気です。
発作は数分から数十分ほどでおさまりますが、「このまま死んでしまうのでは」「気が狂いそう」といった強い恐怖を感じるのが特徴です。
発作が繰り返されるうちに、「また起きたらどうしよう」と不安になり、人が多い場所や電車、閉鎖的な空間を避けるようになります。
これを「予期不安」や「広場恐怖」と呼びます。
パニック障害は決して珍しい病気ではなく、ストレスや生活環境の変化がきっかけで発症することがあります。
日本人の100人に2人程度が経験したことがあり、20~30代の女性に多いようです。
パニック障害はうつ病やアルコール依存症、自律神経失調症などが合併する恐れがあるため、早期発見と早めの治療が重要です。
治療には、薬物療法や認知行動療法などが有効とされ、正しく向き合えば改善が可能です。
適応障害
適応障害とは、ある特定の出来事や環境に対する強いストレス反応が現れる心の病気です。
たとえば、転職・異動・人間関係のトラブルなどがきっかけとなり、不安感や抑うつ気分、イライラ、不眠、食欲不振、涙もろくなるなどの症状があらわれます。
うつ病と似ていますが、原因となるストレスがはっきりしているため、その環境から離れると症状が軽減するのが特徴です。
無理をしてその場にとどまり続けると、症状が悪化し、うつ病などへ進行することもあります。
仕事をやめられないなど、何らかの理由でそのストレス原因から離れることができないと、症状が慢性化する恐れもあります。
不安障害
不安障害とは、日常生活で感じる不安のレベルを大きく超えた強い不安や恐怖が、長期間にわたって続く心の病気の総称です。
「人前に出るのが怖い」「人前で何かをすることに大きな不安や緊張を感じる」「ささいなことで過剰に心配してしまう」といった状態が日常に支障をきたすほどになるのが特徴です。
パニック障害は不安障害の一つで、その他に社交不安障害(あがり症)、全般性不安障害などがあります。
原因は、環境的なストレス、性格傾向や遺伝的要因など、脳内の神経伝達のバランスが関係していると考えられています。
不安障害は、周囲からは理解されにくいこともありますが、れっきとした治療が必要な病気です。
早期の対応と、薬物療法やカウンセリングによる支援によって、改善が見込めます。
睡眠障害
睡眠障害とは、眠りに関するさまざまな問題が続き、心身の健康や日常生活に悪影響を及ぼす状態を指します。
代表的な症状には、
- 寝つけない(入眠障害)
- 夜中に何度も目が覚める(中途覚醒)
- 朝早く目が覚めてしまう(早朝覚醒)
- ぐっすり眠った感じがしない(熟眠障害)
などがあります。
その他には、十分な睡眠をとっているにも関わらず日中過度の眠気に襲われる過眠症や、急に眠気が来るナルコレプシーがあります。
原因はストレスや生活習慣の乱れ、うつ病や不安障害などの精神的な要因、さらには身体の病気や薬の影響など多岐にわたります。
睡眠不足が続くと、集中力や記憶力の低下、イライラ、免疫力の低下などが起こりやすくなります。
慢性的な不眠を放置せず、生活改善や医療機関への相談を通じて、早めに対処することが大切です。
睡眠障害を改善するには、睡眠時間を一定にして生活リズムを整え、健康的な生活を送るのが一番の近道です。
それでも解消しない場合は、薬物治療を行います。
アルコール依存症
アルコール依存症とは、お酒を飲みたいという欲求を自分の意志でコントロールできなくなり、生活や健康に深刻な影響が出ている状態を指します。
単に「お酒が好き」というレベルを超え、飲酒をやめたくてもやめられず、仕事や家庭、人間関係に問題を抱えるようになります。
朝から飲まずにはいられない、飲まないとイライラする、体調が悪くても飲酒を優先してしまうといった行動が見られます。
人間関係や仕事、健康への被害が出て、離婚や辞職の危機に追い込まれても辞められず、社会的に追い詰められてしまいます。
進行すると、記憶障害やうつ状態、肝機能障害などの身体的・精神的な問題にもつながります。
アルコール依存症は意思の弱さではなく、治療が必要な一つの病気です。
専門の医療機関や支援団体を活用すれば、回復と再出発は可能です。家族や周囲の理解と協力も非常に重要です。

精神疾患は、さまざまな要因が複雑に絡み合って発症します。職場でのストレスもその要因になりやすいため、重病になる前に対策を練りましょう。
職場でのメンタルヘルス対策

職場でできるメンタルヘルスケアを紹介します。
何から始めればいいか分からない方は、ぜひこの項目を参考にしてください。
厚生労働省推奨の「4つのケア」について知る
4つのケアとは、厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」で示されているメンタルヘルスケアのことです。
職場でのメンタルヘルスケアを効果的に進めるために必要なケアを、4種類に分けて教えてくれています。
「セルフケア」「ラインケア」「内部EAP」「外部EAP」の4つです。
それぞれどういうものか見ていきましょう。
セルフケア
セルフケアとは、働く人自身が自分のストレスや心の不調に気づき、適切に対処するための取り組みです。
教材を用いて、自分のストレス状況を知り、それをコントロールする方法を学びます。
たとえば、睡眠や食事、運動といった生活習慣を整えることや、リラックス法を取り入れることがセルフケアの一部です。
また、自分のストレスの原因を理解し、気分転換の方法を見つけることも大切です。
会社側は、セルフケアを促すために、ストレスに関する知識や対処法を伝える研修や情報提供を行うことが求められます。
心の不調を悪化させないためには、社員一人ひとりが「まず自分で気づき、対処・コントロールする力」を身につけることが出発点になります。
ラインケア
ラインケアとは、職場の上司や管理職(ライン)が部下の心の健康に気を配り、必要に応じて支援する取り組みのことです。
たとえば、部下の表情や態度の変化に気づき、声をかけたり業務量を調整したりするのもラインケアに含まれます。
さらに、部下との相談時間を設け、深刻な場合は産業医や専門機関につなげる役割も担います。
管理職自身がメンタルヘルスについて正しい知識を持ち、部下の不調に早く気づいて対応することが、職場全体の予防や早期対応につながります。
メンタルヘルス不調の度合いについて知識を付けておくことで、精神に追い詰められる従業員を減らすことにつながります。
会社としては、管理職向けのメンタルヘルス研修や支援体制を整えることが重要です。
内部EAP
内部EAPは、「Employee Assistance Program」の略で、企業が社内に設置する従業員支援プログラムのことで、産業医や産業保健師といった医療専門職からの支援を受けることです。
セルフケアやラインケアの効果を発揮するためには、専門職員との連携が必須です。
社員の健康相談や職場巡視、ストレスチェックの実施・分析、メンタル不調者の復職支援などが主な役割です。
専門的な視点から社員の心身の健康状態を把握し、必要に応じて医療機関との連携や、職場環境の改善提案も行います。
こうしたケアを通じて、早期発見・早期対応につなげることができます。
企業には、産業保健スタッフが活動しやすい体制や、情報共有の仕組みを整えることが求められます。
外部EAP
外部EAPとは、内部EAPの反対で、メンタルヘルスケアを外部の専門機関に依頼することを指します。
外部のカウンセリング機関(EAP)や心療内科、精神科、地域産業保健センター、公的な相談窓口などがこれにあたります。
社内だけでは対応が難しい場合でも、外部の専門家と連携することで、早期の対応や専門的な支援が可能になります。
従業員が会社には相談しづらい時も、外部支援を案内すれば安心して相談できます。
特に中小企業では、こうした外部の力をうまく取り入れることが重要です。
専門職員を雇うより、外部機関を利用したほうがコストを抑えられ、社内の目を気にしなくていいことで従業員も相談しやすいため、外部EAPを利用する会社が増えています。

この4つのケアを行うことで、社内のメンタルヘルスケアの土台が作れます。
何から始めていいか分からない場合はこの4つを準備しましょう。
現状把握と改善行動
まずは、従業員のストレス度合の現状を把握します。
どんな点にストレスを感じるのか、従業員全員と話して、ストレスの原因を探ります。
原因を整理し、ストレス要因としてもっとも多く挙げられている要因から改善していきましょう。
緊急性が高いものを優先的に改善しても構いません。
まずは、自社の現状を知り、どのような改善施策が行えるのかを把握するのが重要です。
メンタルヘルスケアの研修を実施
メンタルヘルスに関する正しい知識や対策方法を、従業員に周知することも大切です。
メンタルヘルスの不調は、周囲の人に気づかれにくく、“単なるずる休み”などと誤解されやすいです。
会社全体がメンタルヘルスに関する正しい情報を持っていれば、そういった誤解が生まれず、安心して休むことができます。
そのために、メンタルヘルスに関する研修やセミナーを開催し、定期的に情報提供を行いましょう。
ストレスチェックを活用する

ストレスチェックは、従業員のストレス度合をチェックし、メンタルヘルスの不調を低減させるツールです。
ストレスチェックの調査結果を集団的に分析することで、職場環境の改善にもつなげられます。
メンタルヘルスケアを取り入れている企業の事例3つ
それでは、企業で行われているメンタルヘルスケアの事例を4つ紹介します。
建設業メインの事例を紹介するので、ぜひ参考にしてください。
村本建設株式会社
道路、ダムなどの土木事業とオフィス、マンションなどの建築事業を中心とした総合建設業。
全国700社ほどの協力会社に現場を任せているけれど、中小零細規模がほとんどで、メンタルヘルスケア対策が十分とは言えない会社が多いです。
そこで、村本建設が管理業務の一つとして、メンタルヘルス対策を実施しています。
【実施していること】
- 建災防方式健康KY
- ストレスチェック制度
- 無記名ストレスチェック(匿名のストレスチェック。その結果を分析して、職場環境の改善を実現する)
- メンタルヘルス推進担当者の養成講座を開催
- 本社でのメンタルヘルスに関するセミナーや説明会への参加
- 役員、社員、協力会社それぞれに向けたメンタルヘルスに関する資料作成と共有」
【結果】
- ・ストレスチェックの分析をして改善策を行ったところ、仕事量は増えても上司の支援も増えたため、ストレスの数値が減少
- ・2019年に、大阪府から「第4回大阪府健康づくりアワード」の表彰を受ける
株式会社千葉正工務店
注文住宅の設計施工やリフォーム工事、インフラ整備などの公共事業も行っている工務店。
建設業界はストレスを抱えやすい業種のため、同業種の人から従業員のメンタルに関する話を聞く機会が増え、本格的にメンタルヘルスのサポートを行う必要があると動き出しました。
【実施していること】
- 外部のストレスチェックや相談窓口の利用
- 毎朝出勤時に従業員の顔を見て挨拶し、様子を確認
- 現場への定期的な顔出し(2日空けない)
【結果】
- ・外部なので話しやすく、従業員のメンタルヘルスケアへ関心も高まっている
- ・外部サービスは経営者の負担削減にもつながる
- ・現場で雑談することで、自然と悩み相談をしてくれることも増えた
株式会社マルケイ
住宅・商業施設・アパート・マンションなどの様々な建物の新築、改修工事を行っている総合建設業。
20代の従業員が増え始めたことをきっかけに、若い世代が長く働き続けられる職場にしたいと考えるようになり、健康経営に取り組み始めました。
【実施していること】
- 週休二日制の導入
- 月1での懇親会の開催
- 社員旅行
- 家族で参加できるイベント(餅つき大会・バーベキューなど)
- 全社員へクリスマスケーキのプレゼント
- ストレスチェックの導入
- メンタルヘルス研修
【結果】
- ・無駄を省いた仕事への取り組みが増え、業績アップ
- ・ストレスチェックの「対人関係でのストレス」や「活気」の項目で改善がみられ、有効な人間関係が構築されている
- ・高ストレス者の減少
- ・ストレスチェックの受講率が4年連続100%、医師による指導の利用実績ゼロ

このように、きっかけも実施内容もさまざまですが、企業に合ったやり方でメンタルヘルス対策を行っています。
これらの企業の成功事例を参考にして、できるものから実施していきましょう。
メンタルヘルスケアを導入する際の注意点

メンタルヘルスケアは、導入すれば改善するわけではありません。
それを踏まえて、注意点を見ていきましょう。
- 制度を作っただけで満足しないこと
- 常に情報収集をすること
- 相談しやすい環境づくりを怠らないこと
- プライバシーへの配慮をすること
- 起こる前に対策する
制度を作っただけで満足しないこと
メンタルヘルス対策の制度を作っただけで満足してはいけません。
メンタルヘルス対策は、使われなければ意味がないですし、周囲がメンタルヘルスを予防する重要性を理解していなければいけません。
使われない前提の制度など、作っても意味がないのです。
また、ストレスチェックの実施、研修、相談窓口の設置など、多方面から対策ができるように、複数の制度を組み合わせましょう。
常に情報収集をすること
人が感じるストレスは、周囲の環境によって目まぐるしく変わっていきます。
環境の変化が起こりやすい現代において、メンタルヘルスに関する情報もどんどん変化していくため、常に情報収集をして、状況に合った対処法を実施していく必要があります。
古い情報のままだと、メンタルヘルスの不調に気づかないリスクがあるので、全社的な情報収集が重要です。
相談しやすい環境づくりを怠らないこと
精神的なストレスや不調というのは、目に見えて分からないものです。
相手に気づかれにくいのはもちろんのこと、自分でも把握できず我慢してしまう可能性があります。
そういった少しの不調でも相談しやすい環境を作っていれば、早期発見ができて鬱病などのリスクを下げられます。
そのためには、やはりメンタルヘルスに関する最新情報を把握している必要があります。
定期的な1on1や、相談窓口の設置など、気軽に相談しやすい職場づくりを行いましょう。
プライバシーへの配慮をすること
精神的な問題は、当事者にとって相談しにくいものです。
誰が相談しているか他の社員に分かったり、上司と顔を合わせて相談したりするのは気が引ける人も多いのではないでしょうか。
そういった気持ちに寄り添い、相談者は匿名で、顔が分からない状態で相談できる窓口を作るなど、プライバシーへの配慮も怠らないようにしましょう。
起こる前に対策する
メンタルヘルスの不調は、一度発生してしまうとなかなか完治させるのが難しいです。
精神的な病気は、本人の心次第な部分もあるため、長引く可能性が高いのです。
そういったことを理解し、不調が起こる前に、会社内でできる十分な対策を行いましょう。
メンタルの不調は気づきにくいからこそ、知っていこう
建設業は、工期に対するプレッシャーが大きく、人手不足などの課題も重なり、ストレスを抱え込む状況に陥りやすいです。
気づいたら鬱病だった、などということにならないように、日頃から従業員の様子をチェックし、気軽に相談できる環境を整えましょう。

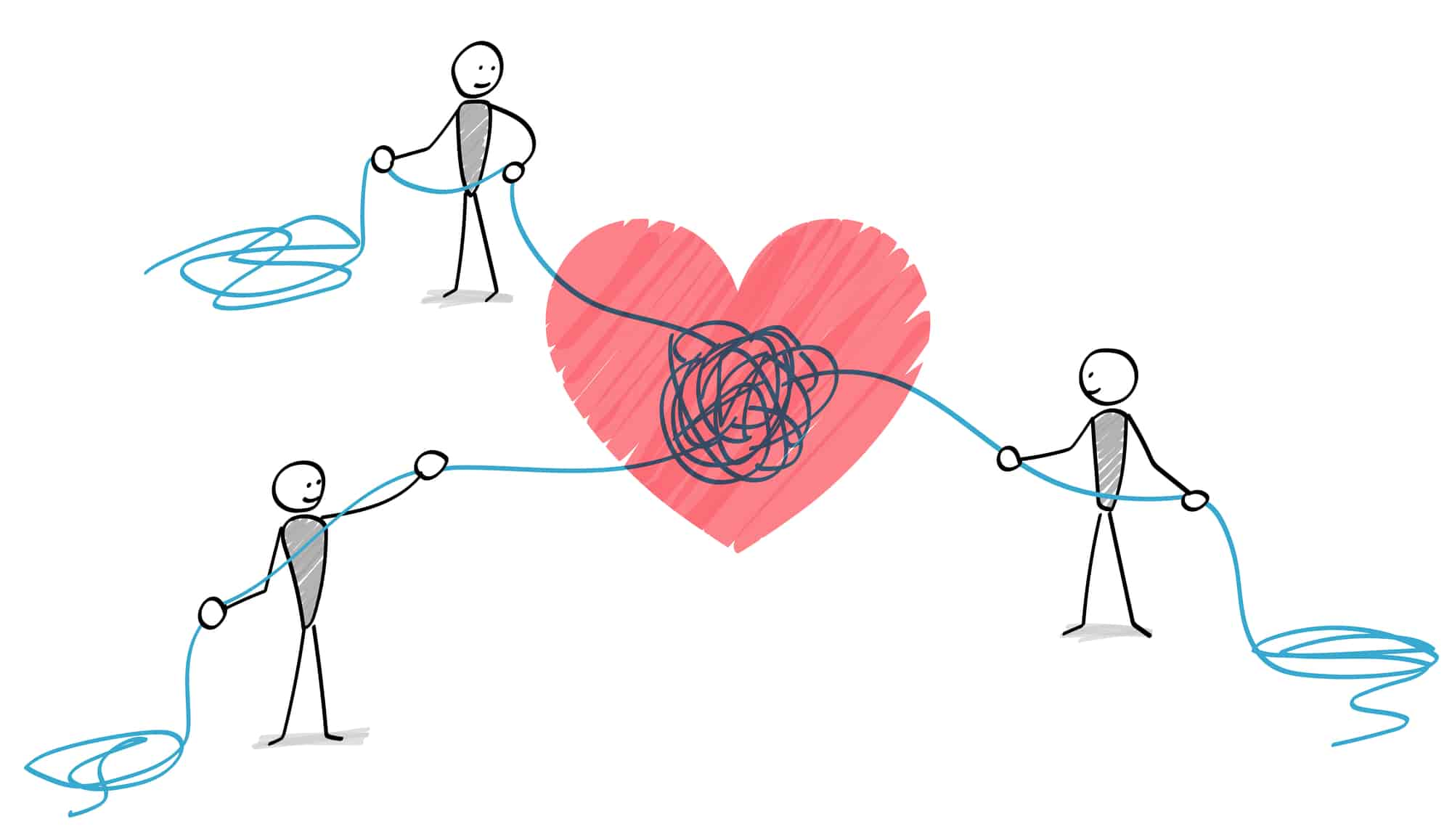
コメント