ウッド・チェンジという言葉をご存じでしょうか。
近年注目度が高まっており、国からも推奨されている取り組みです。
ウッド・チェンジとはどういうものなのか、どんな取り組みが行われているのか知っていきましょう。
建設業にも深く関係のあることなので、知らない方はぜひここで理解していってください♪
ウッド・チェンジとは
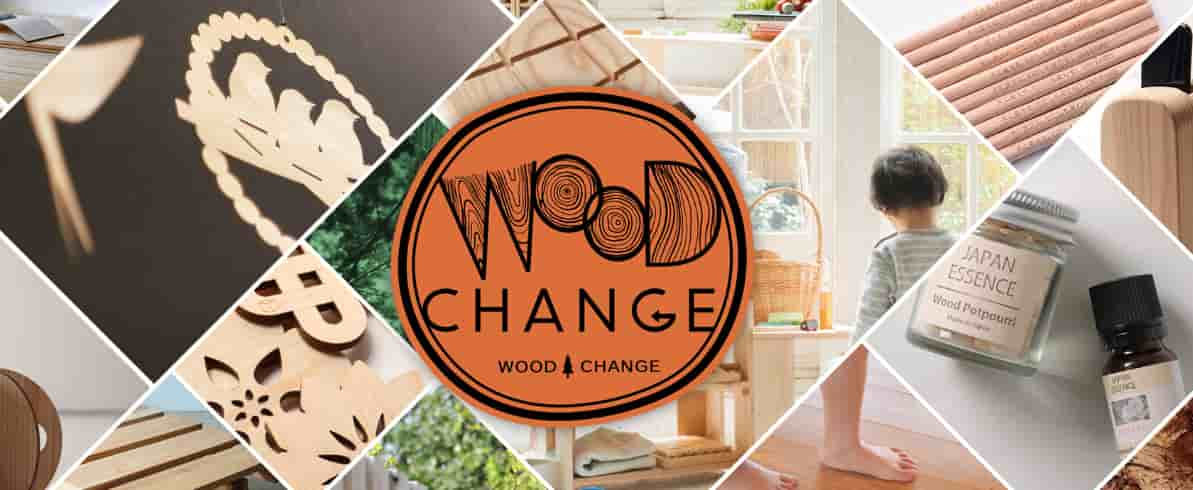
ウッド・チェンジとは、「身の回りものを木に変える」「暮らしに木を取り入れる」「建築物を木造化・木質化する」など、日常に木を取り入れることで持続可能な社会へ変えていく運動のことです。
国内での木材利用を促進するため、2005年に林庁が開始した取り組みになります。
ウッド・チェンジの趣旨に賛同し、積極的な取り組みを行っていることを示す「ウッド・チェンジロゴマーク」も作成しており、使用申請をすればPRに使うことができます。
ウッド・チェンジが注目されるようになった理由
人工林が利用期を迎えている
日本の森林は国土の7割を占めており、その4割が人工林です。
その人工林が今、利用期を向かえているそうです。
森林伐採が問題視されているわけですが、植えて育てた森林はしっかり使ってまた植えて育てるというサイクルを繰り返していくことで山を守ることができるのです。
そのため、国内の木材をしっかり使っていく必要があります。
日本の森林を守るためにも、利用期を迎えた人工林を使っていくことが推奨されているのです。
木造住宅が再評価されるようになった
コロナ過によって自宅時間が増えてことで、木のぬくもりを再評価する人が増えたそうです。
最近は耐震性や耐火性の高い木造建築も増えてきており、デザインの自由度が高く将来リフォームしやすいなどメリットがたくさんあるため、木造建築を選ぶ人が増えています。
SDGs、カーボンニュートラルの促進に繋がる
木というものは、光合成により二酸化炭素を吸収し酸素を排出しながら成長します。
それは木材になってからも変わらず、建物になったとしても二酸化炭素を吸収し続けてくれます。
施工時の二酸化炭素排出量も少ないので、カーボンニュートラルやSDGsの13番「気候変動に具体的な対策を」という目標を促進することができます。
国もウッド・チェンジを推進している!

公共建築物等木材利用促進法の改正により、この法律の目的に「脱炭素社会実現」に役立てる旨を明記し、木材利用促進の対象を公共建築物から建築物一般まで拡大しました。
改正後の基本理念として、
木材の利用促進は森林の循環利用を通じて森林の二酸化炭素吸収作用の強化が図られること、
化石資源の代替材料として二酸化炭素の排出抑制やその他環境負荷の低下が図られること、
森林の多面的機能の発揮や地域経済活性化の貢献に役立つこと
を主として行わなければいけないことが新たに位置づけられました。
また、新たに木材利用促進本部が設置され、令和3年10月1日に基本方針を策定しました。
その他基本方針に基づく措置の実施状況の公表等を行っていくようです。
さらに、10月を「木材利用促進月間」、10月8日を「木材利用促進の日」とすることで積極的な木材利用を促しています。
法の策定により、公共建築物や3階建て以下の低層公共建築物では木造率が年々増加していっています。
非住宅分野や中高層建築物での木造率はまだ低いものの、耐火性や耐震性技術の発達により木造コンビニや木造病院など、木材を利用して造ったぬくもりのある民間建築物が増加しています。
建築物木材利用促進協定制度について
こちらは、建築物における木材利用を促進するために設けられた制度で、建築主等の事業者が国または地方公共団体と「建築物木材利用促進協定制度」を締結することができます。
本協定を締結することで事業者が受けられるメリットは次のものになります。
- 国や地方公共団体による技術的助言・情報提供
- 社会的認知度・評価の向上
- 国や地方公共団体による財政的な支援
- ESG投資などの新たな資金獲得に繋がる
協定締結の手順
- ➀国の場合は農林水産大臣に、地方公共団体の場合は地方公共団体の長に申し入れ書を提出
- ➁申し入れ書の内容が法の趣旨・内容に則しているか確認し、協定締結の応否を国または
- 地方自治体が判断する
- ③申し入れ者と協議を行い、協定内容に係る調整を行う
- ④協定締結セレモニーなど、メディア等へ効果的な宣伝を行う
- ⑤協定を締結した後に内容を公表する(協定の名称・協定参加者の氏名等)
木材供給業者としても、信頼関係に基づくサプライチェーンを構築できる、事業の見通しができて経営が安定化するといったメリットがあります。
ウッド・チェンジの取り組み事例は?
ウッド・チェンジに取り組んでいるのはどんな企業なのでしょうか。
取り組み事例を確認していきましょう。
東京海上日動

東京海上日動は、2016年に地方創生室を創設し全社的な取り組みを行っています。
ウッド・チェンジの活動として、熊本にあるオフィスを熊本県産の木材を使用して建設しました。
エントランス空間において贅沢に木材を使用し、基準階の耐震間柱や窓周りの天井などにも多くの木材を使用しています。
この熊本東京海上日動ビルディングは、2020年にウッドデザイン賞を受賞しています。
マクドナルド

林庁が推奨する「ウッド・チェンジ・ネットワーク」に賛同し、新規出店・改装・建て替えをする店舗の軸組を、鉄骨から木造に切り替えたり外装の一部に木材を使用したりと、可能な限り国産木材を使用しています。
今後は、建設予定の店舗で一店舗当たり一定量以上の地域材を利用する設計を基本とする構想のようです。
今後は鉄骨造りよりも木造のマクドナルドの方が多くなっていくことでしょう。
ナイス株式会社

ナイス株式会社では、今まで「木と住まいの大博覧会」という名称の木材利用促進を宣伝する活動を、東京ビックサイト等で開催してきました。
しかし、コロナが流行してからは会場での開催が困難になりました。
そこで、木材・木造建築に関する情報を発信する「web展示会“木フェス”」を開催したようです。
木材担当者がおすすめの木材製品を動画で紹介したり、7つの県が地域材を紹介したり、多彩な内容で12のセミナーを実施したりと、木材を使用する事業者が欲しい情報を発信したそうです。
Webなのでわざわざ足を運ぶ必要がなく、自宅にいながら木材の情報を取得することができます。
株式会社大林組


大林組では、木の更なる利用拡大を目指し、木材の利用方法のバリエーションを広げているそうです。
都市部で大規模木造建築をいくつも建設しており、2022年には全ての構造材に木材を使用した純木造の高層ビルである「Port Plus」を横浜に建設しました。
11階もあるのは、純木造対価建築物としては国内最高の高さだそうです。
高層木造建築には、高度な耐火性・耐震性が求められる訳ですが、Port Plusには木の柱梁として3時間耐火認定を取得した構造材を採用したそうです。
また、鉄筋コンクリート造りや鉄骨造りと同等の強度・剛性を確保するために、木質の柱梁を剛接合する新技術を開発したそうです。

ウッドショックで価格高騰の問題がありましたが、今は国内木材を使っていくタイミングのようです。
建築物から、木造への関心を高めていこう
木造建築は昔からある日本の伝統的な建築物です。
木のぬくもりを感じられるおしゃれな見た目にできるだけでなく、今の技術では耐震性・耐火性の高い建築物を造ることもできます。
国内の森林を育てるためにも、積極的に木材を利用していきましょう!

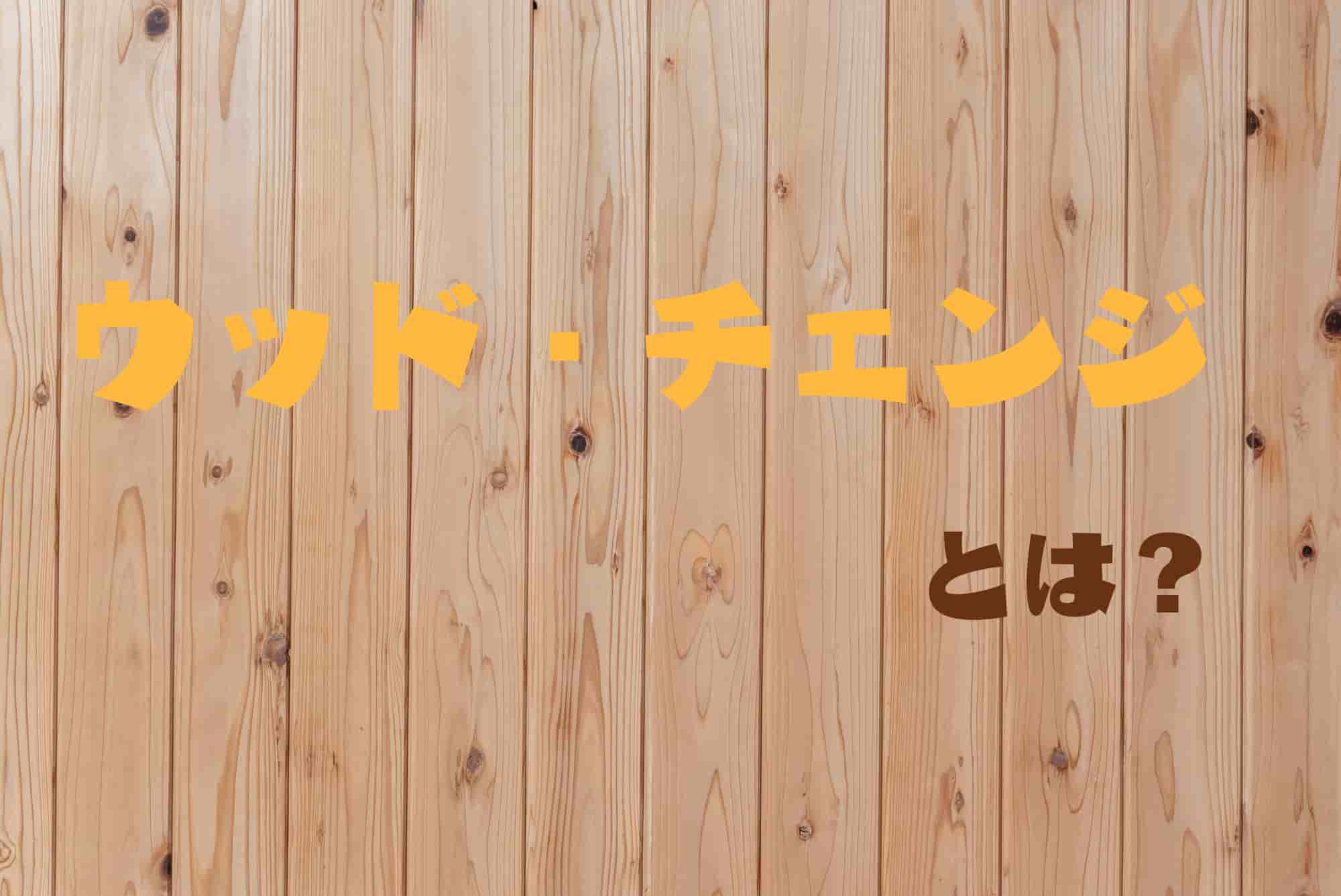
コメント