建設現場は、他業種に比べて事故発生リスクが高いです。
まさかのところに潜んでいる危険もあります。
それらを事前に発見、対策して事故を未然に防ぐには、「危険予知活動(KY活動)」が必要なのです!
今回は、建設業で欠かせない危険予知活動について解説します。
危険予知活動(KY活動)とは

危険予知活動とは、職場や現場で発生する事故や災害を未然に防ぐために行う活動のことです。
危険の「K」と予知の「Y」をとって「KY活動」とも言われています。
従業員の安全や健康を守るために欠かせない活動であり、建設業などの危険が多く事故発生リスクが高い職場では、必ず取り入れるべきものです。
厚生労働省では、KY活動のことを以下のように説明しています。
その後、対策を決め、行動目標や指差し呼称項目を設定し、一人ひとりが指差し呼称で安全衛生を先取りしながら業務を進めます。このプロセスがKY活動です。」
危険予知活動(KY活動)の目的は、職場や現場に潜む危険を発見・共有してみんなで対策を考えることで、従業員の安全に対する意識を向上し、事故発生リスクの低下、作業効率アップ、チームワーク向上を図ることです。
一般的にKY活動が行われている業種は以下のものです。
- 建設業
- 電気工事業
- 製造業
- 医療業
リスクアセスメントとの違い
リスクアセスメントとは、
「現場作業における危険性と有害性を特定し、それによる労働災害の重篤度と発生確率の度合いを組み合わせてリスクを見積もります。
そのリスクの大きさに基づいて対策の優先順位を決めた上で、リスクの除去または低減措置を検討し、その結果を記録する一連の手法のことです。」
と厚生労働省によって説明されています。
リスクアセスメントの目的は、従業員全員で職場の危険やそれに対する対策を実施し、職場にある災害リスクをできるだけ除去することです。
KY活動と似ている点が多いですが、KY活動よりも時間やお金をかけてじっくり行うものであり、根本的な問題を解決するための手法です。
KY活動も危険やリスクをなくすためのものですが、現場作業員のために現場の危険を迅速に把握し予防するものです。
また、リスクアセスメントは原材料や作業内容、危険有害性等が変化した時に実施することが義務付けられています。
一方、KY活動は毎日または作業ごとに実施されます。

危険予知活動をするメリット

KY活動を行うことで、どのようなメリットがあるのでしょうか。
理由も分からずやっても、真剣に取り組まないので意味がありません。
KY活動をするメリットを今一度確認し、従業員全員の意欲を高めましょう!
危険意識の向上
KY活動は基本的に毎日行われるので、危険箇所はないか探す癖がつきます。
現場が変わっても、新しい機械が導入されても、その意識は継続されるので、気づかないうちに危険への意識が高まります。
従業員全員の危険への意識が高まると、事故発生リスクを大幅に下げることができます。
問題解決能力の向上
毎日危険箇所を探して対策を考えるので、自然と課題発見と問題解決能力が養われます。
問題解決能力は他業務でも活用できる能力なので、スキルアップの機会になります。
いろんな人と話し合って意見を言い合うという経験も、他の業務に活かせるものなので、KY活動を通してさまざまなスキルを身に付けられます。
チームワークが高まる
従業員全員で話し合いをしてお互いに本音の意見を言い合うことで、コミュニケーションの機会になり仲が深まります。
また、お互いに危険を意識して声を掛け合うなどのコミュニケーションも自然と生まれるため、チームワークが高まり作業効率アップにつながります。
職場環境が良くなる
お互いに意見を言って話し合う時間を毎日設けられるので、コミュニケーションが活発になり風通しのいい職場づくりにつながります。
「職場をよくするための活動に参加している」という帰属意識も強くなり、モチベーションアップにもなります。
「危険をなくす」という一つの目標に向かって進んでいくので、仲間意識が向上して職場全体が盛り上がります。
今から始められる♪危険予知活動の進め方

KY活動を行う際は、「KYT基礎4R法」という基本手法が使われます。
問題解決を4つのラウンドに分けて、段階的に進めていきましょう。
ラウンド1 現状把握
まずは、職場や現場にどんな危険が潜んでいるかを洗い出します。
イラストや写真をチームメンバーで確認しながら、危険箇所を自由に言い合います。
どういう行為や状況が危険なのか、理由を追及して核となる危険因子を見つけていきましょう。
人数が多い方が気づきも増えるので、なるべく大人数で現状把握を行いましょう。
ラウンド2 本質追求
ラウンド1で洗い出した危険の中で、危険度が高いと思われるものに〇をつけます。
最も危険度が高い、要注意ポイントだと思うものに◎をつけて波線を引きます。
◎をつけたものがどういう風に危険なのかをみんなで話し合い、危険箇所に対する理解度を深めましょう。
ラウンド3 対策樹立
ラウンド2で理解を深めた危険箇所に対する対策を考えます。
どうすればこの危険を回避できるのか、排除できるのか、具体案をチームで出し合います。
その際、「具体的な策になっているか」「社内で実現可能か」の2点を意識することで、より具体的で現実的な意見を出し合うことができます。
ラウンド4 目標設定
ラウンド3で挙げた対策を基に、具体的な行動目標を立てていきます。
いくつかある対策の中で優先順位を決め、最も実現性が高いものを目標に設定します。
この際、現場の従業員がすぐに実行できるものを目標に掲げるようにしましょう。

ここまでできたら、最後に危険箇所を指差し確認し、従業員全員が危険箇所と対策方法を把握できたら終了です。
普段働いている場所の危険についてじっくり考える時間を持つことで、今後の事故発生リスクを減らすことができます。
危険場所のネタ切れ・・・どうすればいい?ネタ切れ防止のコツ
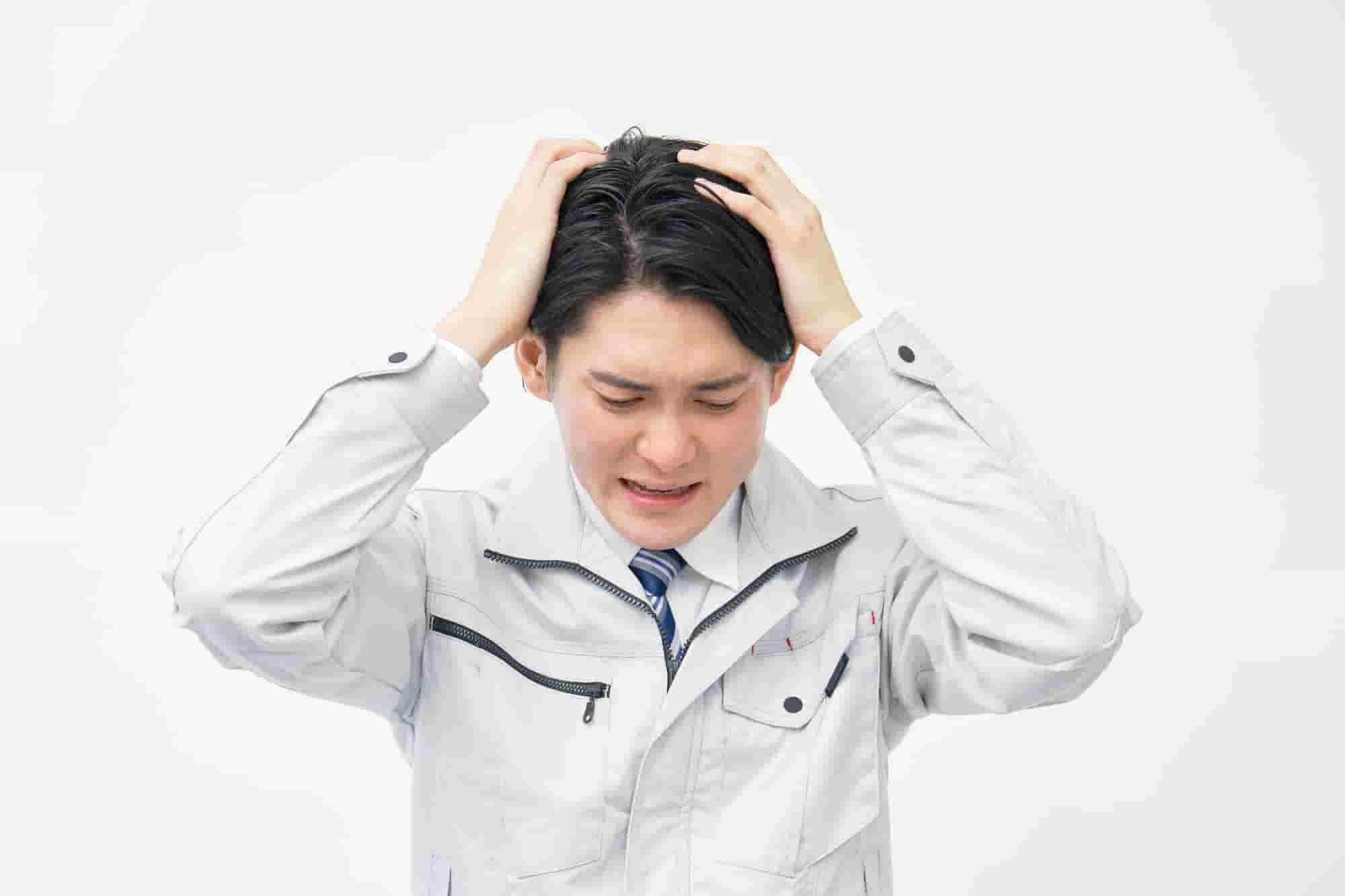 KY活動は毎日行われ、定期的に内容を変えて危険に対する意識を更新する必要があります。
KY活動は毎日行われ、定期的に内容を変えて危険に対する意識を更新する必要があります。
最初こそ危険箇所に関するたくさんの意見が出ると思いますが、日が経つごとに把握済みの危険箇所が多くなり、危険箇所を見つけるのが難しくなってネタ切れを起こしてしまいます。
その際はどうすればいいか、ネタ切れの対策方法を知っていきましょう。
些細なヒヤリ・ハットを発見する
「ヒヤリ・ハット」とは、仕事場で「ヒヤッとした」「ハッとした」などの危険体験のことを指します。
事故に発展する一歩手前の出来事なので、些細なものでも従業員の体験を集め、その中からKY活動につながるものを洗い出しましょう。
実際に起きた労働災害を参考にする
現場で実際に起きた災害は、どの現場でも起こりうるものです。
自分の現場で同じような危険箇所がないか、従業員が危険を把握できているかを確認することで、潜んでいた新たな危険を発見することにもつながります。
各現場の事例を確認することで、より多くの危険予知活動につながるのでおすすめです。
報告しやすい環境を作る
従業員が、小さな危険やヒヤリ・ハットでも報告しやすい環境を作りましょう。
「この危険は些細なことすぎるしな…」と遠慮して伝えない人がたくさんいると、現場に潜む危険を見逃してしまいます。
小さな危険が大きな事故につながる可能性もあることを従業員全員に伝え、どんな小さなことでも危険だと感じたらすぐ報告するように、定期的に呼びかけましょう。
問題内容を細分化する
今まで発見した一つの問題や危険を細分化することで、問題解決の核心にたどり着けるかもしれません。
また、問題が分岐して新たな問題を発見したり、新たな解決策を発見したりもできます。
大きな問題の方が細分化しやすいと思うので、ぜひ一度試してみてください。
アプリを使って効率的に危険を共有しよう♪
KY活動をより効率的に行うためには、アプリの活用がおすすめです。
アプリには、下記のような機能があります。
- アプリ内でのKY活動シートの作成
- AIによる危険ポイントの提案
- PDFでの保存・共有
- 入力補助
- タブレットやスマートフォンから内容確認ができる
このように、データで共有できるので、場所に縛られずいつでも好きな時に入力・確認できます。
データなので紛失や汚れることもなく、安全に保管できます。
AIを搭載したものもあるので、KY活動のネタ切れ対策にもつながります。
「これからKY活動に力を入れたい」
「KY活動の内容がマンネリ化している」
「現場で紙の書類を確認するのが大変」
このような希望・悩みがある方はぜひ、アプリの導入を検討してみてください♪


コメント