建設工事を行う上で、工事発注者と受注者の間でさまざまな書類が交わされます。
その中で注文書は、契約上のトラブルを避けるために必要な重要書類です。
注文書はなぜ必要なのか、作成方法、保管方法など、注文書に関して知っておくべき知識を紹介したいと思います。
注文書とは

注文書(工事注文書)とは、建設業において工事発注者が受注者に対して交付する契約書の一つです。
商品名・金額・数量・納期など、工事の契約時に必要な情報が記載されています。
注文書を発行することで契約内容が明確になるため、契約後のトラブルを防ぐことができます。
基本的に注文書は契約申し込みの意思を確認するために取り交わされるものなので、原則注文書単体では法的効力がなく、契約が成立したことにはなりません。
そのため、注文書を交付する前に事業者間で「基本契約書」を取り交わしている場合がほとんどです。
基本契約書とは、企業間で継続的に取引を行う時に、一連の取引で共通する約束事を取りまとめた契約書のことです。
基本契約書に約束事の詳細が載っているので、注文書はその時の工事内容のみで細かいルールは記載しません。
なお、注文書の発行は工事を注文する発注者が行います。
注文請書との違い
注文請書は、受注者が注文書の内容を引き受ける証明として発注者に送る書類です。
注文書は工事の発注者によって発行され、注文請書は工事の受注者によって発行されるという違いがあります。
注文書と注文請書を取り交わすことによって契約書としての効力を発揮し、契約が成立します。
そのため、承諾の期間を定めずに注文書の発行(契約の申し込み)を行った場合、注文請書を交付しなければその契約は不成立になります。
ただし、次の場合は注文請書を交付しなくても契約が成立します。
- すでに基本契約を締結している場合
- 常日頃から取引をしているお得意先が、自社の商品・サービスの発注(契約の申し込み)を行った場合

契約書との違い
注文書と契約書、どちらも契約の証明を行うための書類です。
しかし、契約書はそれ一つで法的効力を持ち契約の証明となりますが、注文書はそれ一つでは法的効力を持たないという違いがあります。
また、注文者書は工事内容や金額などの記載がメインですが、契約書は契約後の機密保持、契約解除事由、損害賠償など、契約する上でトラブルが起きないような決まり事の記載がメインです。
契約書では契約時のルールを決められるので、万が一トラブルが発生した際にもめることなく処理することができます。
余計なトラブルを避けるためにも、契約書の締結をおすすめします。
注文書はなぜ必要?

注文書の交付は義務ではありませんが、工事を行う上で必要な書類です。
なぜ必要なのか、それは主に次の2つの理由があります。
- 発注の意思決定を明確にし、取引成立を証明するため
- 工事内容のトラブルを防ぐため
発注の意思決定を明確にし、取引成立を証明するため
契約後に注文書と注文請書を取り交わすことで、契約が無事成立したことを明確にすることができます。
取引が成立したことを書面に残せるので、お互いに安心してやりとりできます。
工事内容のトラブルを防ぐため
契約は注文書がなくても行えますが、それだと具体的な工事の内容が不明瞭なまま工事が行われることになります。
そうなると、発注者と受注者の間で認識の違いが発生するリスクが高く、トラブルにつながりやすいです。
そういったトラブルをなくすためにも、工事内容を明確にしてお互いの認識をすり合わせられる注文書の交付が必要になるのです。
注文書の作成方法
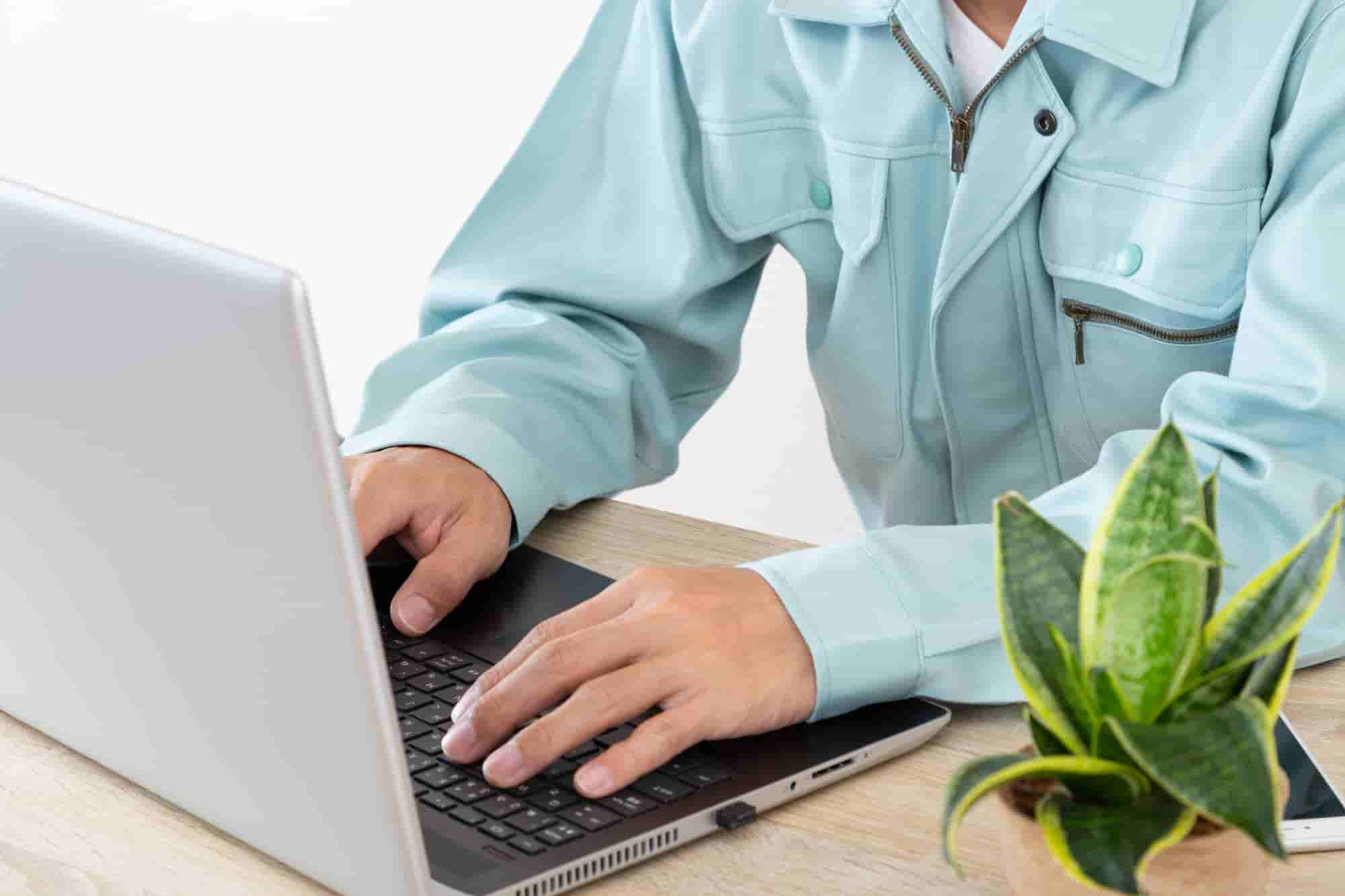
では、注文書はどのように作成すればいいのか見ていきましょう。
注文書には次の項目を記載する必要があります。
- タイトル(「注文書」「発注書」など)
- 宛名(受注企業名)
- 注文ナンバー(社内で割り振っている場合は記載)
- 発行日
- 工事名
- 工事内容
- 工期
- 施工場所
- 発注金額
- 発注者の企業名・住所・電話番号・メールアドレス
- 支払い方法
- 支払い条件
- 発注する商品名・仕様・数量・単価・金額
- 備考
備考欄は必要ない場合も多いですが、注意点や共有事項がある時に役立つので用意しておくことをおすすめします。
市販の複写簿で作成する
市販で複写式の注文書が売っているので、そちらを使って注文書を作成できます。
記載内容は固定なので、枠を追加するなどカスタムすることはできません。
一般的に記載が必要な項目は揃っていると思いますが、必須の項目がある場合は中身を確認してから購入することをおすすめします。
平均1冊(50組)で500円未満のものが多いです。
Excel・Wordで作成する
ExcelやWordなどの既存ソフトで作成することもできます。
無料で作ることができてデータとして残せるので、紙よりも管理が楽です。
注文書の型を作っておけば、オリジナルのテンプレートとして利用できます。
Excelだと計算式が使えるため、金額の部分で手間を省くことができます。

管理ツールを利用する
最近は受発注管理ツールが増えてきており、作成だけでなく商品管理やデータ出力、システム連携など受発注管理に必要な機能が搭載されています。
データとしてクラウド上に保存できるので、紙のように紛失したり汚したりするリスクがないためツールでの作成・管理がおすすめです。
クラウドサインという電子契約サービスでは、注文書のひな形・テンプレートを用意しているので簡単に注文書を作成できます。
その他、事前にやり取りをして注文書と注文請書をまとめたデータをクラウドサイン上にアップし、発注者と受注者がお互いに同意することで電子署名・電子スタンプをつけ、電子契約を結ぶことができます。
クラウドサインについて、詳しくはこちらをご覧ください。

注文書は保管が必要!保管方法を知ろう

注文書は、国税関係書類に該当するため一定期間の保管が必要です。
法人の場合、事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から数えて7年間の保管義務があります。
ただし、次の項目に当てはまる場合は保管期間が10年になります。
- ・青色申告書を提出した事業年度に欠損金が生じた、または欠損金の繰越控除を受ける場合
- ・青色申告書を提出しなかった事業年度に災害損失損金が生じた
つまり、法人の場合は10年間保管するつもりでいることをおすすめします。
個人の場合、事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から数えて5年間の保管義務があります。
なお、帳簿や決算関係書類などは7年間の保管が必要になるので、それに合わせて注文書も7年間保管してもいいでしょう。
保管方法
クリアファイルやバインダーにまとめる
紙のまま保管する場合は、クリアファイルやバインダーに年度ごとまとめるのがいいでしょう。
年度ごとにまとめておけば後で確認する時に探しやすいですし、汚れるリスクを下げることができます。
ただし、毎年追加されていくものなので、管理場所が必要になる、量が増えるたびに探すのが大変になる、といったデメリットもあります。
スキャンしてデータとして保存する
コピー機でスキャンして、データとしてファイルにまとめておくという方法です。
これなら保管場所も必要なくなり、検索もしやすいです。
注文書を作成してすぐにスキャンにかければ、特に手間なく保管できます。
ただし、保存期間が長いためデータ容量が膨大になって容量が圧迫され、パソコンの動きに影響が出る可能性があります。
クラウドツールを使って保存する
クラウド上にデータを保存する方法です。
一元管理ができて検索も簡単ですし、クラウド上なのでデータ容量を圧迫することもありません。
ただし、インターネットを経由するのでセキュリティ対策が必要不可欠になります。
クラウドツールを利用する場合は、セキュリティ対策をしっかり行っているか確認してください。
なお、上記で紹介したクラウドサインでは、無料プラン・有料プランに関わらず無制限でデータ保存が可能です。
もし保管をしなかったら・・・
保管をしなかった場合、経費として処理していても証拠不十分として税金を追加徴収される可能性があります。
それを防ぐためにも、必ず保管を行いましょう。
要確認!注文書作成の注意点

注文書を作成する上での注意点を紹介します。
作成後に困ったことにならないように、事前に確認しておきましょう。
下請法が適用となる取引では発行義務がある
注文書の作成は義務ではないといいましたが、下請法が適用となる場合は発行が義務付けられています。
下請法とは、経済的に上の立場にある発注者の権利濫用行為を規制することで、受注者の経済的利益を保護することを目的とした法律です。
下請法の対象となる取引には種類があり、双方の資本金によって適用範囲が異なります。
資本金が1000万円を超える企業が一人親方などの個人事業主に依頼する際は注文書の発行が必須になると思っておいてください。
下請法が適用するにも関わらず、注文書の作成・交付・保管を怠った場合は50万円以下の罰金が科せられます。
印紙を貼り付けることを忘れない
注文請書を作成する際、収入印紙の貼り付けが必要になります。
注文請書は受注者が発行するものなので、収入印紙の購入も受注者が行います。
注文請書に貼り付ける収入印紙の金額は、契約金額によって異なります。
1万円以上100万円以下のものは200円、5000万円を超え1000万円以下のものは1万円など、細かく金額が分けられているので事前に確認してから購入してください。
なお、1万円未満の契約に関しては収入印紙が不要です。
万が一収入印紙の貼り付けを忘れてしまうと、納税義務違反となり過怠税が課せられます。
本来必要な印紙税の金額+その2倍に相当する金額の合計額を支払う必要があるので、当初払うべき金額の3倍の額を支払う羽目になってしまうのです…!
金額が大きいほど違反時の負担も大きくなるので、貼り付けることを忘れないようにしてください。
なお、クラウドサインなどの電子契約では収入印紙税が発生しなくなります。
データなので印紙税がかからないという理由で、収入印紙の貼り付けが不要となります。
記載ミスがあった場合は再発行する
記載ミスがあった場合、修正して提出するのではなく新しく注文書を発行するのが一般的です。
修正線が引かれているものより、奇麗なものを送った方が相手からの印象も良くなります。
電子帳簿保存法の保存方法に従う
注文書の保管に関しても、電子帳簿保存法が適用されます。
紙で送られてきた注文書は紙で保管できますが、データで送られてきた注文書は電子で保管することが義務付けられています。
電子での保管方法としては、送られてきたシステム上での保管・PDFデータでの保管・スクリーンショットによる保管などの方法があります。
いずれにしても、次の要件を満たす必要があります。
- ・システム概要を記載した書類を備え付ける
- ・見読可能装置(パソコンやディスプレイなど)の備え付け
- ・改ざん防止措置をとること(タイムスタンプの付与・訂正削除の記録が残るシステムを利用する)
- ・日付、取引先、金額で検索できるようにすること
見積書を見ながら記載する
注文書を作成する際、受注者から見積書をもらって金額や工事内容などを確認しながら同じように記載しましょう。
そうすることで見積書と相違のない内容で注文書を作成できます。
見積書にある見積番号を一緒に記載すると、さらに間違いが発生しにくくなります。
まとめ
注文書の発行・交付は、契約後にトラブルをなくすために必要なものです。
義務ではないからといって発行しなかったり適当に作成したりしてしまうと、後から受注者ともめるリスクがあります
注文書も契約書の一つだと意識して、丁寧に作成しましょう。
なお、注文書の作成は電子データで行うのがおすすめです。
電子データであれば、注文書の作成や管理が楽になるだけでなく、収入印紙にかかる費用も抑えられるためメリットが大きいのです!
電子契約なら「クラウドサイン」がおすすめです。
作成だけでなく電子契約、管理まで一貫して行うことができるのです!
詳しくはこちらで、クラウドサインの機能や評判をご覧ください。



コメント