今回は、建設業で発生する外注について、外注の特徴や外注費などを中心に解説していきたいと思います。
外注とは

外注とは、会社内の仕事を社外の人に手伝ってもらうことです。
自社よりも専門的な技術を持つ企業に作業の一部を任せる場合に使われる言葉です。
下請けとの違い
まず、元請けと言われる仕事を発注して外部に依頼する会社があります。
外注の場合、元請けからの依頼を受けた後は会社内で指示を出して作業を行います。
一方、下請けは元請けからの依頼を受けた後は元請けの指示を聞いて作業を行います。
外注と下請けの違いは、「指示がどこから出るか」の点で大きくことなるのです。
業務委託との違い
外注は、上記でも説明したように社内の仕事を外部に手伝ってもらうことを広い意味として使われています。
一方業務委託は外注の一部であり、依頼された仕事をこなして納品する契約形態のことを言います。
内容としては一緒ですが、外注の中に業務委託契約というものが存在すると覚えておきましょう。
外注を使うメリット・デメリット
では、外注を使うメリット・デメリットを知っていきましょう。
メリット
業務の効率化
仕事を成功させるためには、直接利益を生み出す「コア業務」とサポート的役割をしている「ノンコア業務」の両方をこなしていく必要があります。
このどちらにも人員を割いていると、コア業務に注力することができずに機会損失が起こる可能性が高いです。
ノンコア業務を外注に任せることで、コア業務に集中することができるのです。
人手不足の解消
建設業は人手不足が深刻です。
特に職人が足りない企業が多いので、外注することで人手を補充し、現場の人手不足を解消することができます。
コストの削減
外注を利用することで、人材採用にかかるコストや固定の人件費が削減できます。
外注の場合は雇う人数を調整できるので、繁忙期は外注で人を多く雇い、閑散期は外注利用を控えることでコストを抑えることができるのです。
技術のある人材を雇うことができる
社員として採用する場合、若手の場合は特に未経験が多く一から教えるため即戦力にはなりません。
中途採用で経験者を雇う場合も、採用までに時間がかかります。
外注の場合、スキルや経験を持った人員をすぐに雇うことができるので、余計なコストがかからず質のいい仕事をしてもらうことができます。
もし微妙な人材だった場合も、外注の場合は短期間の契約なので別の人材にすぐ変更することができます。
デメリット
認識の齟齬が生まれやすい
外注は社員ではないため、業務の進め方や意識に対して共感してもらえないことがあります。
作業をスムーズに行うためには、認識が合っているか、コミュニケーションがしっかり取れるかも意識して外注先を選びましょう。
情報漏洩の恐れ
外注を依頼する場合、外部の人に企業の情報を共有する必要があります。
そのため、機密情報が外部に漏れる可能性があることを知っておきましょう。
契約する際に、企業の情報を外部へ漏らさないことを条件に入れておいたり、外注者にも情報漏洩をしないように伝えておいたりすることが重要です。
もちろん、社内でもセキュリティソフトの導入など、情報漏洩対策を徹底しておきましょう。
こちらでおすすめのセキュリティソフトを紹介しているので、一緒にご覧ください。

いい外注先が見つからない可能性
外注者はさまざまな企業から仕事を受けているため、タイミングによっては依頼を受けてもらえない可能性があります。
特に繁忙期は依頼数も多くなるので、気に入った外注先があるなら関係性を築いて早くから予約をとっておくといいでしょう。
社内人材が増えない
外注にばかり頼ってしまうと、社内人材が増えなかったり、育成ができずに社内従業員のスキルが上がらなかったりという弊害が出てしまいます。
外注ばかりに頼り切るのではなく、社内人材をメインで考えるようにしましょう。
一人親方への報酬は給与?外注費?
一人親方を継続に雇用する場合もあると思いますが、その場合の報酬は給与になるのか、外注費になるのか気になるところですよね。
「外注として雇っているなら外注費でしょ?」と思う人が多いと思いますが、場合によっては給与に該当する場合もあります。
その違いは、「外注している一人親方が事業者と認められるかどうか」です。
事業者は、個人で生計を立てている者のことを言います。
もし契約形態が雇用契約に近い場合、一人親方の外注であっても報酬は「給与」と判断されてしまいます。
なお、外注費の場合は課税仕入れとして仕入税控除の対象となり節税になりますが、給与の場合は控除の対象外となります。
また、外注費であれば源泉徴収が必要ありませんが、給与の場合は必要です。
外注費に当てはまる一人親方の定義
では、外注費に該当するかどうかはどこで判別されるのでしょうか。
➀一人親方が行う業務の遂行または役務の提供において、他人が代替できること
一人親方に任せている業務が、その人でなくてもできる場合は外注費と判断されます。
一方、任せている業務がその人でなくてはできないものである場合は、給与と判断されます。
➁報酬を支払う事業者からの指揮監督を受けていないこと
雇用者からの指示を受けず、独立して仕事をしている場合は外注費と判断されます。
なお、軽微な指示や事故防止のための指示であれば指揮下にあるとは判断されないため
外注費となる可能性が高いです。
一方、作業内容の大半を指示されている、報酬が時間単位で支払われるなど時間的拘束をされ
ている場合は給与として判断されます。
③引き渡しが完了していない物件等が不可抗力でなくなった場合に、既に遂行した業務や提供した役務に対して報酬を請求できないこと
例えば、建物の完成前に災害によって倒壊してしまった場合、それまで遂行した業務に
対しての報酬をせいきゅうすることができない場合は、外注費として判断されます。
一方、このような場合でも一定の報酬を得られる場合は外注よりも従業員にカテゴライズ
されるため、給与と判断されます。
④役務の提供に係る材料または用具を雇用者から提供されないこと
工事に利用する用具や材料などを自分で用意しているなら外注費と判断されます。
一方、必要な材料や用具を雇用者によって用意してもらっているなら給与と判断されます。
外注費とその仕訳について
一般的な会計では、1年間で区切って業績を計算します。
しかし、建設業の場合は工事に1年以上かかることが多いため、一般的なものとは違った会計をしなければいけません。
この建設業独自の会計を「建設業会計」と言います。
建設業会計では、建設業法施行規則という法律で定められた勘定項目を用いらなければなりません。
建設業会計において、売掛金は完成工事未収入金になり、買掛金は工事未払金になるなどいろいろありますが、外注に対して注目すべきは完成工事原価です。
外注費は完成工事原価に当てはまる!
一般会計では売上原価にあたる完成工事原価ですが、この中には材料費・労務費・外注費・経費が含まれます。
建設業では業務を外注することが多いため、売上原価において外注費が占める割合が多いためこの中に含まれているのです。
ただし、完成工事原価の外注費として計上するのは、外注者が必要な材料や用具を全て自分で用意した場合のみです。
材料の一部を除いて雇用者が用意したり、人手不足による人材支援で雇用したりした場合は臨時雇用とみなされるため、「労務外注費」として処理することになるので注意しましょう。
【仕訳例】
外注費300,000円で作業を依頼した。なお、材料費は全て他社が用意した。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 外注費 | 300,000 | 工事未払金 | 300,000 |
要確認!外注を使う際の注意点
最後に、外注を使う際に注意する点を紹介します。
外注の場合、元請の労災保険が適用されない
一人親方などの外注者であり雇用契約にない場合は、元請が入っている労災保険が適用外となってしまいます。
そのため、個人事業主のように「一人親方労災保険」が用意されているのです。
この保険に入るのは任意ですが、万が一外注業務中に怪我をした場合、一人親方労災保険に入っていないと莫大なお金がかかってしまいます。
建設業では高所や不安定な場所での作業が多く事故の発生リスクが高いため、元請け側も外注者に対して一人親方労災保険に入るよう促すようにしてください。
外注でも下請法が適用になるケースがある
下請法とは、経済的に優位な立ち位置にある新規事業者による下請け業者に対する濫用行為を取り締まるための法律です。
取引当事者の資本金と取引内容に対して、条件を満たす場合に適用となります。
物品の製造・修理委託および政令で定める情報成果物・役務提供委託を行う場合
資本金3億円超の新規事業者が資本金3億円以下の下請け業者に依頼する
または
資本金1千万円超3億円以下の新規事業者が資本金1千万円以下の下請け業者に依頼する
情報成果物作成・役務提供委託を行う場合
資本金5千万円超の新規事業者が資本金5千万円以下の下請け業者に依頼する
または
資本金1千万円超5千万円以下の新規事業者が資本金1千万円以下の下請け業者に依頼する
メリット・デメリットをしっかり把握して外注を活用しよう!
外注は、従業員よりも融通が利きやすくメリットが多いです。
しかし、デメリットや注意すべき点もあるため、しっかり把握してから雇用するようにしましょう。
外注を使うことで効率的に人手を足していってください!
職人不足なら、建設業向けマッチングサービスがおすすめ♪
なお、職人が不足していて悩んでいるならマッチングサービス「KIZUNA」をぜひご活用ください!
知人の紹介だけでは交流を持てない数の職人と出会うことができます。
シンプルな掲示板で職人の応募もしやすく、完全審査制なので安心してやりとりできます!
無料なのでまずは一度使って実感してみてください♪

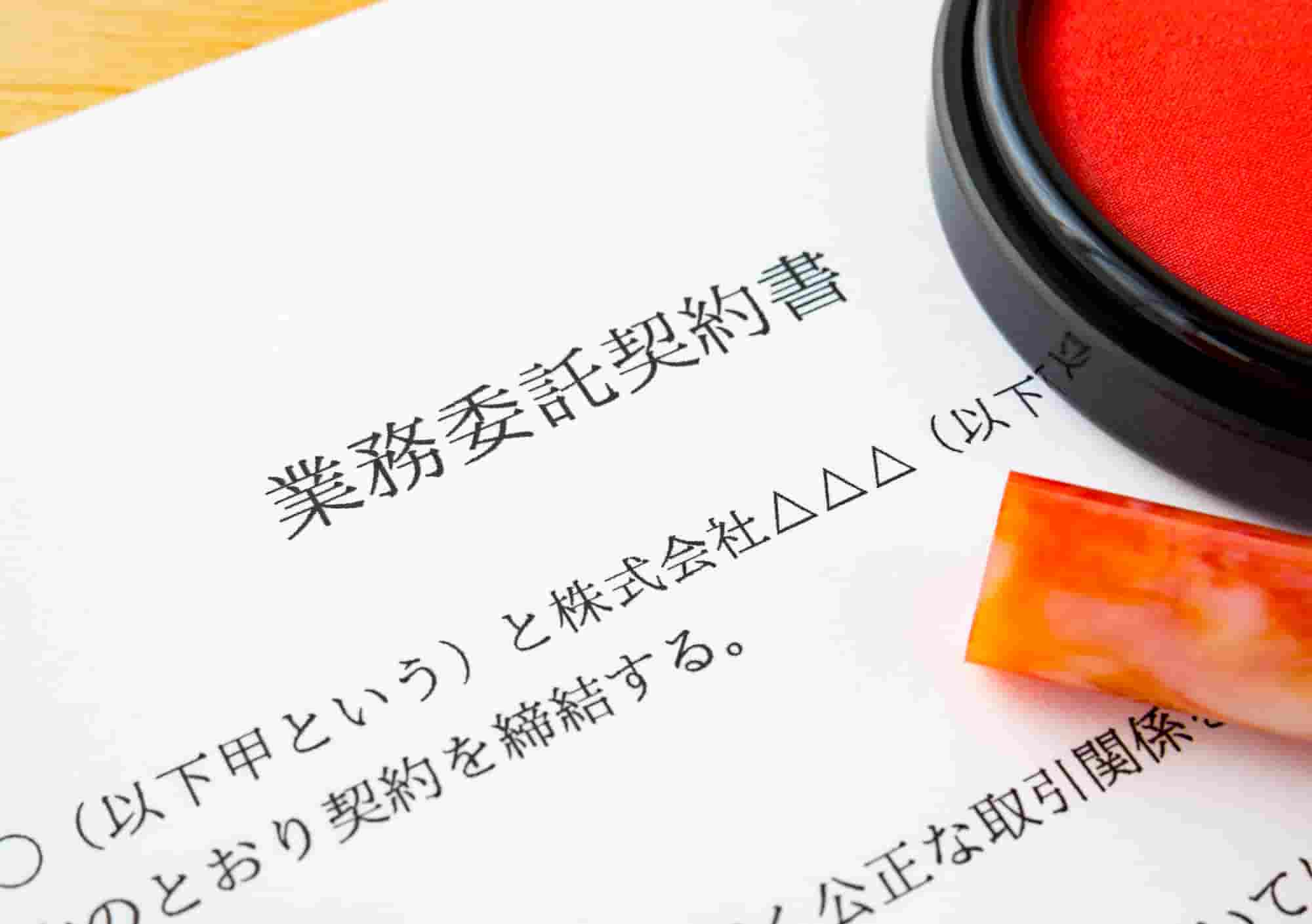
コメント