マイホームや土地の買い取りを検討している方は、「防火地域・準防火地域」という言葉を聞く機会が多いと思います。
火災を防ぐために法律で指定されている地域のことですが、
一体どんな地域なのか、そこに建てるメリット、建築制限など、防火地域・準防火地域に建物を建てる際の基準を知って、違法にならないように準備していきましょう!
防火地域とはどんな場所?

防火地域とは、都市計画法において市街地や住宅密集地での火災を防ぐために指定された地域のことです。
駅前や建物の密集地、幹線道路沿い、繁華街、重要な公共施設周辺などがその地域に指定されます。
繁華街や駅は火が周囲に燃え移りやすいため、幹線道路は火災の際に緊急車両の進行を妨げないようにするため、公共施設は重要なインフラや行政施設を守るためなど、火災が起きた時のリスクが大きい場所が防災地域に指定されています。
防火地域と準防火地域の違い

防火地域と準防火地域は、火災の危険度や建築物の規制レベルが異なります。
防火地域
市街地や駅周辺など、特に火災発生時の危険性が高い地域が指定されています。
そのため、建築基準も厳しくなります。(これについては次の項目で話します。)
防火地域では、鉄骨造や鉄筋コンクリートの建物がメインで、木造の建物はほとんどありません。
準防火地域
準防火地域は、防火地域よりも幅広い範囲が指定されていますが、建築基準や規制は防火地域よりも緩くなっています。
準防火地域は、延焼速度を遅くして市街地の火災を防ぐために指定されています。
そのため、木造住宅も2階建て程度なら建てることができます。
法22条区域と新防火地域との違い
防火地域・準防火地域の他にも、法22条区域と新防火地域という指定地域があります。
それぞれどんな地域なのか見ていきましょう。
法22条区域とは
建築基準法22条で指定された区域のことで、火災の延焼を防ぐ目的があります。
防火地域や準防火地域に指定されていない市街地が対象です。
建物の屋根を不燃材料で造るという規制があるため、「屋根不燃化区域」とも呼ばれます。
新防火地域とは
木造密集地域において、特に地震によって発生する火災などによる危険性が高い地域のことです。
東京都のみに設けられた地域であり、防火地域の次に規制が厳しいです。
防火地域には建築制限がある!

防火地域・準防火地域では、建物の高さや面積によって耐火性のある建物にする必要があります。
防火地域と準防火地域では制限内容が異なる部分があるので、それぞれ見ていきましょう。
【防火地域の建築制限】
3階建て以上、または延べ床面積が100㎡を超える建物は、耐火建築物にしなければいけません。
| 階数/延べ床面積 | 50㎡以下 | 100㎡以下 | 100㎡超 |
| 3階以上 | 耐火建築物 | 耐火建築物 | 耐火建築物 |
| 2階 | 準耐火建築物 | 準耐火建築物 | |
| 1階(平屋) | 防火構造※1 |
※建築基準法第61条参照
※1物置や車庫などの付属建築物の場合
【準防火地域の建築制限】
3階建て以上、または延べ床面積が500㎡を超える建物は、耐火建築物または準防火建築物にしなければいけません。
| 階数/延べ床面積 | 500㎡以下 | 500㎡以上1500㎡以下 | 1500㎡超 |
| 4階以上 | 耐火建築物 | 耐火建築物 | 耐火建築物 |
| 3階 | 一定の防火措置※1 | 準耐火建築物 | |
| 2階以下 | 防火構造※2 |
※建築基準法第62条参照
※2:隣地境界線等から1m以内の外壁の開口部に防火設備、外壁の開口部の面積は隣地境界線等からの距離に応じた数値以下、外壁を防火構造として屋内側から燃え抜けが城市内構造、屋根・屋根の直下の天井は燃え抜けが生じない構造、3階の室の部分とそれ以外の部分とを間仕切壁または戸で区画することが必要。
※3木造建築物の場合
木造は建てられる?
木造であっても、耐火構造の家を建てることはできます。
主要構造部分に燃えにくい木材を使う、柱や梁の耐火性能を確保する、窓や扉の開口部に防火設備を設置するなど、十分な耐火性能を付与することができれば大丈夫です。
ただし、建築確認申請時に構造計算書や耐火構造証資料等の提出が求められる場合があり、耐火構造の木造建築物に対する審査はかなり厳しくなっています。
耐火構造を確保するのも手間と費用がかかるので、 防火地域で木造を建てるのはあまりおすすめできません。
地域にまたがる場合はどうなる?
場合によっては、防火地域と準防火地域、準防火地域とそれ以外の地域をまたいで建てられている場合もあるでしょう。
この場合は、原則としてより制限の厳しい地域の規定に従うことになっています。
例えば、一つの建物が防火地域と準防火地域をまたいで建てられた場合、建物全体に防火地域の規制が適用されます。
ただし、建物を防火区画ごとに明確に分離した場合や構造上独立させた2棟として建てた場合は、それぞれの地域ごとの規制を適用できます。
建物の基準について

上記の建築制限において、「耐火建築物」「準耐火建築物」「防火構造」という単語が出てきたと思いますが、それぞれどういう建築物のことなのか説明します。
耐火建築物
火災が発生しても、一定時間倒壊・崩壊・延焼しない建築物のことです。
以下の条件を満たす必要があります。
- 主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根・階段など)がすべて耐火構造である
- 使用する建材や構法が国土交通大臣の認定を受けているまたは告示で定められた仕様である
- 窓等の開口部を防火窓や防火ドア、防火ダンパー付き換気扇である
- 耐火時間が原則1時間以上
鉄筋コンクリートや鉄骨造のものがほとんど。
準耐火建築物
火災発生時に、ある程度の時間建物の倒壊・延焼を防ぐ性能がある建築物のことです。
- 主要構造部(壁・柱・床・屋根など)の一部が耐火構造である
- 使用する建材や構法が国土交通大臣の認定を受けているまたは告示で定められた仕様である
- 窓等の開口部で延焼のおそれがある部分に、防火戸や防火設備が設置してある
- 耐火時間が原則30~45分
防火構造
火災発生時に、隣接した建物や外部からの延焼を一定時間(30分以上)防ぐ性能を持つ建築構造のことです。
主に、建物の外壁・軒裏・屋根などの、外部からの延焼ダメージを受けやすいところに要求されます。
必見!防火地域・防火地域に家を建てるメリット・デメリット
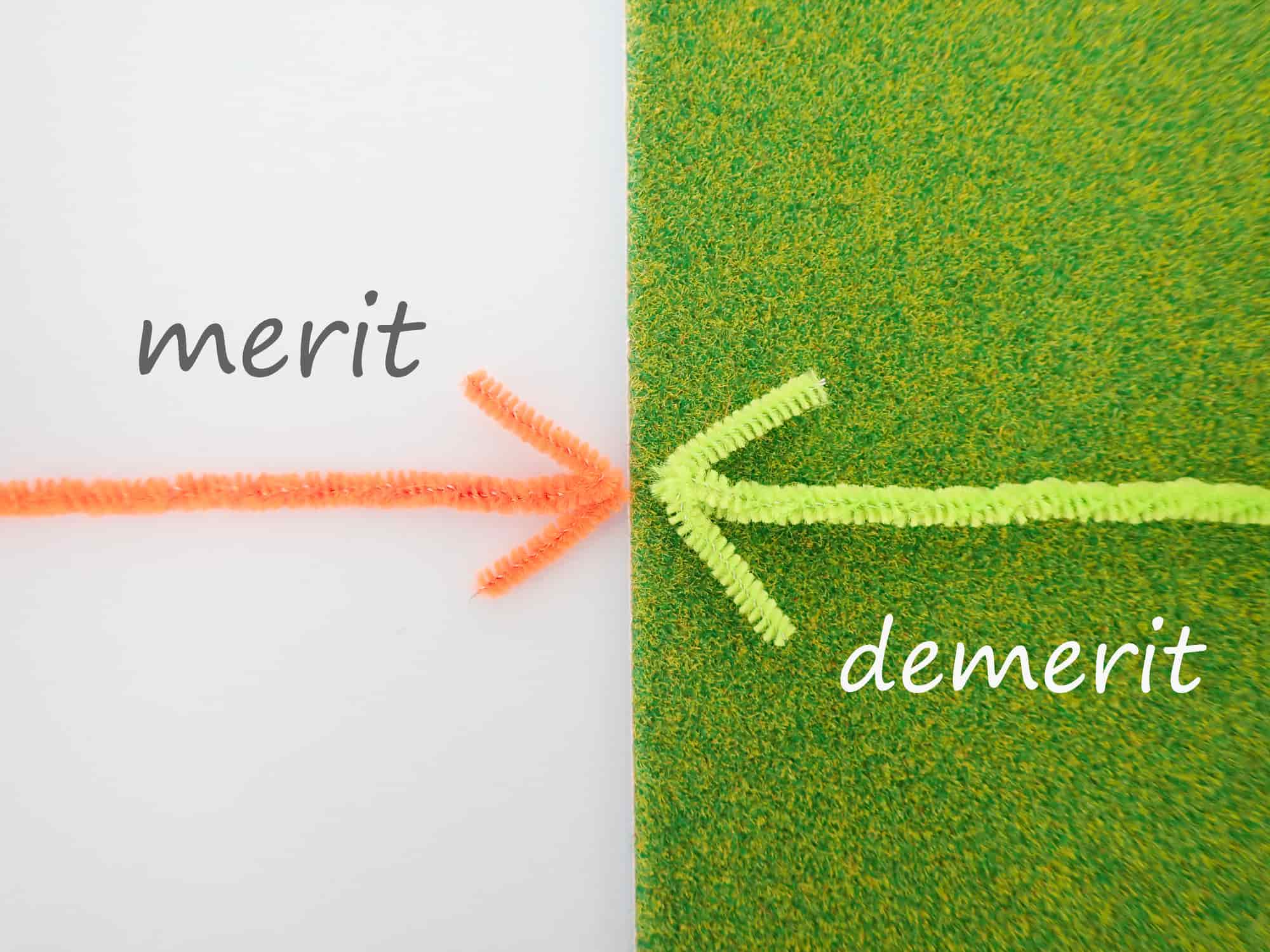
建築制限があって申請も必要な地域なので、普通であればあまり建てたくないと感じるでしょう。
しかし、防火地域・準防火地域に建てるメリットがあるのです!
もちろんデメリットもあるのでどちらも確認していきましょう。
メリット
火災リスクを減らせる
防火地域や準防火地域に建築する場合、強制的に耐火性能の高い建物にする必要があります。
そのため、万が一の場合も、火災による被害を抑えることができます。
建ぺい率が緩和する
建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合のことです。
耐火地域・準防火地域の建物は、建ぺい率が10%緩和されるので、それ以外の地域より大きな建物を建てることができます。
火災保険料が安くなる
耐火地域や準防火地域では、耐火構造のしっかりした建物が建てられるため、保険会社から火災のリスクが少ないと判断され、保険料が安くなることが多いです。
資産価値が高くなる
防火地域・準防火地域は、市街地や駅チカなどの好立地なので、建物の資産価値が高いです。
もし引っ越しすることがあっても、高く売ることができるでしょう。
デメリット
建築費用が割高
地域における耐火性能の基準を満たすには、上質な木材や防火設備を用意する必要があります。
そのため、防火地域外に建物を建てるよりもコストがかかってしまいます。
その分建物の質が上がるので、安心して暮らし続けられるというメリットもあります。
デザインが制限される
基準に合った耐火性能を持たせるためには、構造や家の配置も制限される可能性があります。
そのため、外壁の仕上げ材や大きな窓の設置など、やりたいデザインが制限される可能性があります。
建築確認申請が必要なケースが多い
建物が規定に合った耐火構造を有しているか、建築確認の申請が必要になります。
建築確認で不許可になった場合は、建築計画を見直す必要も出てくるので、建てるまでに時間がかかる可能性があります。
よくある気になる質問にお答えします!

防火地域・準防火地域において、よくある質問にお答えします!
防火地域・準防火地域に建設を考えている方、ぜひ確認していってください。
防火地域・準防火地域が定められる前に建てられた建物は、構造を変更しなくていいのか
防火地域に後からなった場合、既存の建物の構造をすぐに変更する義務はありません。
ただし、以下の場合は現在の規制に従う必要があります。
- 増築した場合:増築部分に耐火・準耐火性能が必要
- 大規模改修:建物全体または一部に規制適用
- 用途の変更:用途が変わると防火基準も変わるため、規制適用の可能性あり
- 老朽化による建て替え:建て替えは新築扱いなので、規制適用
窓や扉を開閉した時に延焼ラインにかかってしまっても平気?
その場合は、その状態も考慮して防火対策をする必要があります。
建築基準法において、延焼の恐れがある部分は「隣地境界線・道路中心線から1階は3m以内、2階以上は5m以内、平屋は1階5m以内にかかってくる部分」とされています。
この範囲内にある窓・扉・壁などには、防火構造を施す必要があります。
隣地境界からどれくらい距離を保つ必要がありますか?
建物自体は、隣地境界ギリギリでも建てることができます。
ただし、防火構性能を付ける必要があります。
物置の設置はOK?
防火地域・準防火地域でも、物置を設置することができます。
ただし、大きさや設置場所によって耐火構造が必要になります。
延べ面積が10㎡を超える場合、原則として耐火建築物にすることが求められます。
また、その場合建築確認申請が必要になります。
店舗併用住宅の耐火性能は、一般住宅と異なる?
防火地域・準防火地域では、店舗部分に対してより厳しい耐火性能が求められる場合が多いです。
店舗部分が延焼ラインにかかる場合、防火構造や防火戸が必須になります。
まとめ
 防火地域と準防火地域は、建物に耐火性能を持たせることが必須になります。
防火地域と準防火地域は、建物に耐火性能を持たせることが必須になります。
コストと手間がかかりますが、その分火災に強く、保険料節約、建ぺい率の緩和など、メリットも多いです。
防火地域と準防火地域は、市街地や駅周辺など住みやすい場所が指定されているので、快適に生活することを一番に考えるのであれば、その地域に建てるのもいいと思います。
「やりたいデザインがある!」という場合は、防火地域・準防火地域は選ばない方がいいでしょう。
自治体によっては、インターネット上で防火地域・準防火地域を調べることができます。
建物を建てたいと思っている地域が防火地域・準防火地域に指定されているか、事前に確認してみてください。


コメント