電気工事士は、私たちの生活に欠かせない電気を建物に通し、メンテナンスを行う職業です。
しかし、詳しい仕事内容や資格について、知らない人も多いでしょう。
そこで、この記事で電気工事士を紹介していこうと思います。
ここで魅力を知って、電気工事士を目指してみてください♪
電気工事士とは

電気工事士とは、建物に欠かせない電気関連の工事をする仕事です。
住宅やビル、工場などの建物において、電気を安全に使用できるように工事や管理を行います。
配線設備工事、照明器具の設置、家電取り付けなど、電気工事と言ってもさまざまな仕事があります。
弱電工事と強電工事がある
電気工事には、大きく分けて「弱電」と「強電」の二つの種類があります。
弱電は48V以下の電圧を取り扱う工事で、以下のような工事が該当します。
- LAN配線工事
- テレビ配線工事
- インターホン設備
- 防犯設備設置工事
一方、強電は48V以上の電圧を取り扱う工事で、以下のような工事が該当します。
- 照明設備工事
- 空調設備設置工事
- 受変電設備工事
- エレベーター・エスカレーターの設備工事
- 避雷設備工事
このように、弱電工事と強電工事でできる電気工事の幅が異なります。

強電工事のスキルを持っている方が、大規模な工事にも携われるので、転職にも強く年収も高い傾向にあります。
どちらを選ぶかは、自分の興味や働き方で決めていきましょう。
仕事内容
上記の工事内容で分かるように、電気工事士の仕事は一言では言い表せないほど幅広いです。
仕事内容としては、「建築電気工事」と「鉄道電気工事」の二つに大きく分けられます。
建築電気工事

官公庁施設、工場、ビル、事務所、住宅、病院など、さまざまな建物の屋内外電気設備の配線や設置、メンテナンスを行います。
- コンセントやスイッチの取り付け
- 空調設備の設置
- 変電設備の配線
- 制御回路のメンテナンス
- 家電の取り付け
- LANや電話の配線
- インターネット回線の敷設
新築の場合は配線などゼロから工事を行いますが、既存の建物の場合は新しく配線を増やすなどリフォーム・改修工事を行います。
鉄道電気工事

鉄道に関わる電気工事を行います。
- 信号機の設置・交換・点検
- 踏切や駅内の照明工事
- 架線(鉄塔と鉄塔の間に張られている電線のこと)工事
- 電力供給設備工事
- 変電設備工事
工事だけでなく、定期的なメンテナンスも行います。
電車が動いている時はできない作業なので、夜間に行われることがほとんどです。
電気工事士という仕事の魅力について

電気工事士の仕事のイメージが湧いたところで、この仕事の魅力を知っていきましょう。
もっと興味が出ること間違いなしです!
社会を支える仕事
現在、社会で使われているほとんどのものが電気で動いています。
私たちが毎日使っているスマートフォンやパソコンも、電気がなければ使えません。
建物も、照明や空調がなければ快適に過ごせません。
電車においても、電気がなければ動くこともできませんし、信号が正常に作動しなければ事故発生リスクが高まります。
このように、生活に欠かせない電気を通してメンテナンスを行うことが電気工事士の仕事です。
社会にとって欠かせない存在であり、社会を支える重要な役割を担うことができます。
手に職をつけられる
仕事の幅が多いため、覚えることもたくさんあります。
しかし、知識や経験を身に付けていくことで、一人で通電までできる人材に成長できます。
手に職がつくので、職を失いリスクを減らすことができ、独立などキャリアの選択肢を広げられます。
将来性がある
現在でも、生活の中で電気が欠かせない存在になっているわけですが、今後さらにIT化が進んでいくことを考えると、電気工事士の仕事がなくなることはありません。
加えて、再生エネルギーへの注目が高まっており、積極的な導入が推奨されています。
太陽光発電や風力発電、電気自動車の充電スタンドなど、これらの工事や点検を行うのも電気工事士の仕事です。
これらが今後も増えていくと考えられるため、電気工事士の需要も高まっていくでしょう。
毎回達成感を得られる
電気工事では、配線や設備設置など、さまざまな作業を経て建物に電気を通します。
自分の知識とスキルをフル活用して、電気が通った時の達成感を毎回感じることができます。
また、大規模工事の場合はチームで協力しながら工事を行うこともあります。
チームのメンバーと一丸となって作業を進め、大型ビルなどの電気工事が完了した時は、みんなで喜んだり労ったりと、チームだからこその達成感も感じられます。
電気工事士は資格が必要?
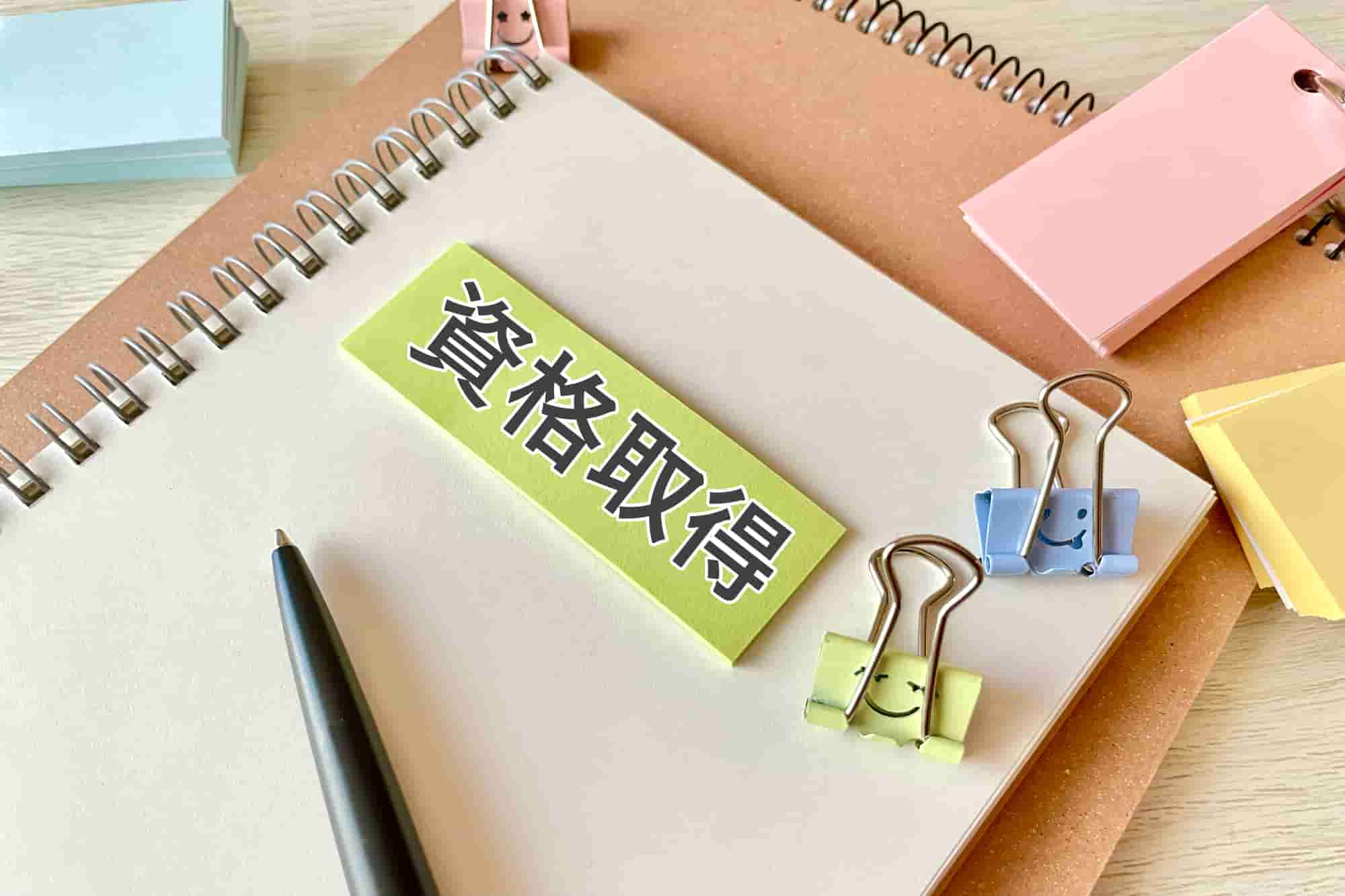
電機工事士になるには、電機工事士の資格取得が必要です。
電機工事士の資格は、「第一種電気工事士」と「第二種電気工事士」に分類されています。
電機工事士の資格は国家資格の一つですが、国家資格の中では難易度が比較的低いようです。
第一種・第二種、どちらも合格率が比較的高いので、独学でも十分に合格を狙えます。
それぞれどのような違いがあるのか見ていきましょう。
第二種電気工事士
一般住宅や小規模施設、小規模店舗など、600V以下で受電する設備の電気工事を行えます。
具体的には、屋内の配線工事、照明機器の設置、エアコンの設置、屋内外の電線やコンセントの配線などができます。
第二種電気工事士の資格があると、現場代理人になれたり自宅のリフォームができたりします。
現場代理人とは、現場における最高責任者のことです。
電機工事士としてスキルを伸ばすだけでなく、人に指示を出すリーダースキルも身に付けたい方は、第二種を取得することで経験を積めます。
第二種電気工事士は、第一種よりも難易度が低く、合格率は学科試験で60%前後、技能試験は70%前後と高い数値で推移しています。
【受験資格】
特になし
年齢や学歴、職歴関係なく誰でも受験できます。
【合格基準】
学科試験では、60点以上が合格基準です。
50問のうち30問以上正解していれば合格です。
技能試験では、出題された配線図を時間内にミスなく施工できていれば合格です。
【免状交付の条件】
実務経験は不要なので、合格後すぐに交付申請ができます。
【勉強時間】
勉強時間の目安は、筆記と技能試験を合わせて100~200時間程度です。
第一種電気工事士
第二種電気工事士のできることに加えて、最大500キロワット未満の建物の電気工事ができます。
配線やコンセントの設置に加えて、エレベーターなどの大型機材の設置・点検が行えるようになります。
以下のような建物での工事が可能になります。
- 戸建て住宅
- 小規模店舗
- ビル
- 工場
- マンション
- 商業施設
- 公共施設
第二種電気工事士で取り扱える建物に加えて大規模建築の電気工事も行えるので、活躍の場がかなり広がります。
第二種電気工事士より難易度が上がり、合格率は学科試験で40%前後、技能試験で60%前後です。
しかし、そこまで低い数値ではないので、しっかり勉強して対策すれば合格できます。
【受験資格】
特になし
年齢や学歴、職歴関係なく誰でも受験できます。
【合格基準】
学科試験では、60点以上が合格基準です。
50問のうち30問以上正解していれば合格です。
技能試験では、出題された配線図を時間内にミスなく施工できていれば合格です。
【免状交付の条件】
試験合格に加えて、3年以上の実務経験が必要です。
連続ではなく合計3年以上あればいいので、ブランクがあっても大丈夫です。
試験合格前の期間も含まれるので、第二種電気工事士としての実務経験が3年以上あれば、試験合格後すぐに免状を申請できます。
なお、実務経験として認められるのは以下の工事です。
- 第二種電気工事士として行う一般電気工作物等にかかる電気工事
- 認定電気工事者として行う最大電力500kW未満の自家用電気工作物の低圧部分にかかる電気工事
- 最大電力500kW以上の自家用電気工作物にかかる電気工事
- 第二種電気工事士養成施設において、教員として担当する実習
【勉強時間】
勉強時間の目安は、筆記と技能試験を合わせて300時間以上です。
電気工事士の年収について
電気工事士の年収はどのくらいか気になりますよね。
第二種電気工事士は平均年収300~450万円で、第一種電気工事士は平均年収400~500万円と言われています。
年収を上げるには、経験を積んで役職につく、上位資格を取得する、大規模工事を取り扱っている会社に転職する(ただし第一種電気工事士とある程度の経験が必要)などの方法が考えられます。
こちらの年収はあくまで目安なので、経験や任される仕事のスケール次第で変動します。
年収をどんどん上げていきたい人は、第一種電気工事士取得を目指しましょう!
どういう人が向いている?
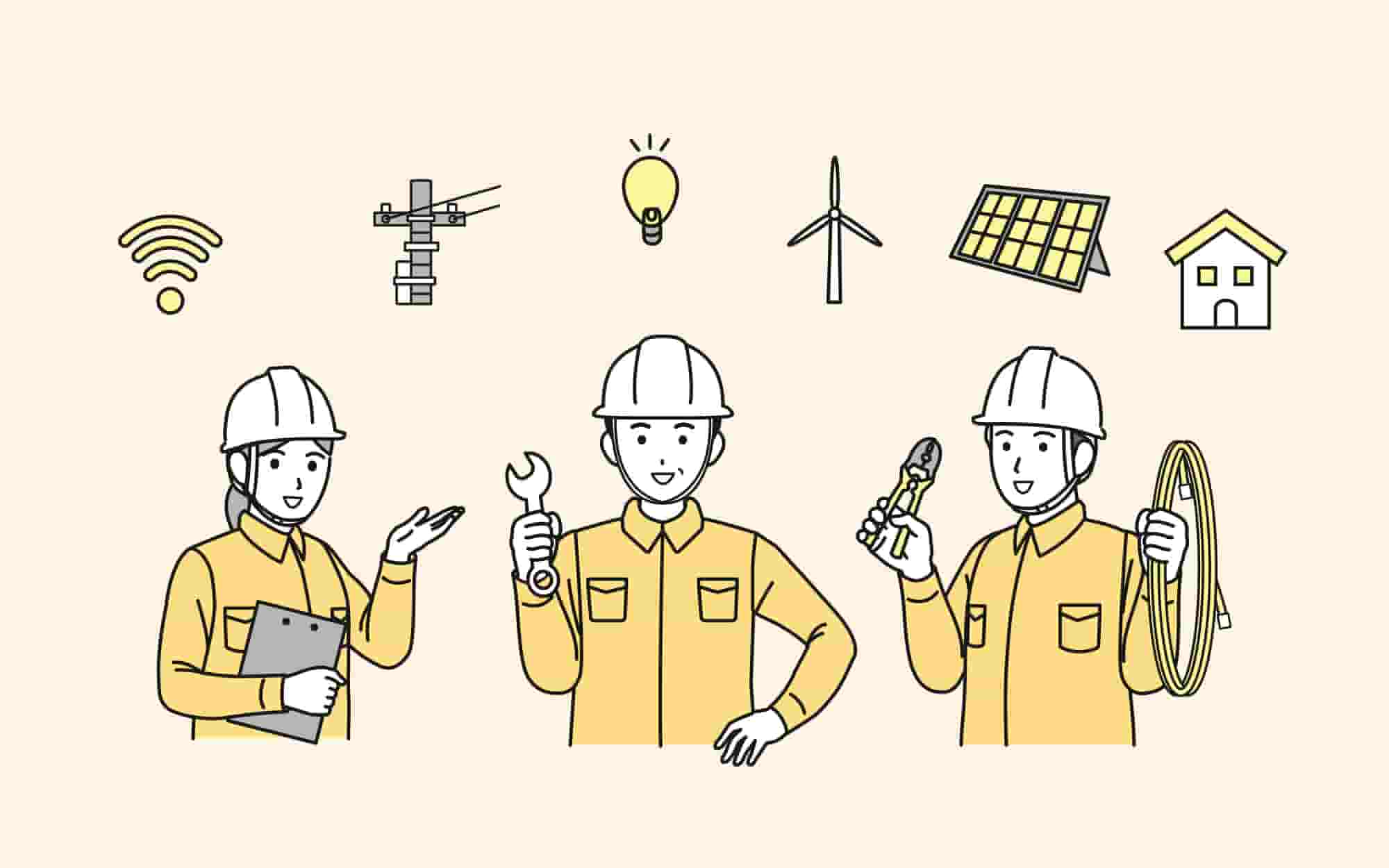
電気工事士を今から目指そうという前に、どういう人が向いているのか知っておきたいですよね。
自分が向いているのかを知っておいた方が、目指しやすくもなるでしょう。
向いている人の特徴を紹介するので、ぜひ参考にしてください。
電気工事に興味がある人
やはり、第一に電気工事に興味がないと続けていけません。
「子供の頃、電気回路のおもちゃで遊ぶのが好きだった」「DIYをするのが好き」「車やバイクをいじるのが好き」
などなど、こんな些細なことで構いません。
自己分析の一環として、電機工事への興味があるかどうか、一度自分に問いかけてみてください。
几帳面な人
電機工事の仕事は、ケーブルの取り付けや絶縁処理、アース線の設置など、非常に細かい作業が多いです。
図面通りにきっちり作業を進められる人でなければ、事故や電気が通らないといったトラブルが起きてしまいます。
手先が器用で几帳面に作業を進められるだけでなく、事前準備を怠らず先回りしてトラブル発生を予防できる人が向いています。
コミュニケーションがしっかりとれる人
電気工事の作業中は、他作業員とのコミュニケーションも重要です。
工事前の確認事項を伝え合う、指示に従って臨機応変に対応する、自分の作業状況を分かりやすく伝えるなど、人と話すスキルというよりも相手とその場に応じたコミュニケーションができる人が向いています。
「無口だから…」と目指すのをあきらめる必要はありません。
周りの人としっかり情報共有をしながら作業を進められる能力がある人に向いています。
集中力に自信がある人
電気工事では、ケーブルを何十メートルにも渡って敷設することもあります。
上記で言ったように細かい作業も多いので、何時間も集中して作業をする必要が出てきます。
大規模工事になると、配線や設備設置の数ももっと増えて工事にかかる時間も増加します。
そのため、長時間集中して細かい作業ができる人が向いています。
新しいことを学ぶことが好き
電気工事士は仕事内容が幅広いので、さまざまなスキルが求められます。
覚える知識が多いので、一人前になるにはかなりの時間がかかるでしょう。
また、工法や道具などの専門用語も多いため、他職人に言われた時にすぐ分かるように勉強する必要があります。
新しいことを学ぶのが好き、コツコツ勉強するのが苦ではないという方は、電気工事士に向いています。
電気工事士を目指そう!
電気工事士は、将来性もあり手に職がつくので将来の選択肢も幅広く、資格取得でスキルを伸ばしていける、働き甲斐のある仕事です。
工事完了時は常に達成感を感じられるのもこの仕事の魅力です。
電機工事に興味があるのでしたら、迷う理由はありません。
ぜひ一人前の電気工事士を目指してみてください!
独立後は、KIZUNAで仕事をゲット♪

もし電気工事士として独立をしたら、まず探さなければいけないのは仕事ですよね。
元職場からの紹介はあるでしょうが、紹介には限りがあります。
そこで活用してほしいのが、建設業向けマッチングサービス「KIZUNA」です!
完全審査制で、信用できる企業様しか登録していないので、安心して取引ができます。
シンプルな見た目の掲示板でやり取りできるので、「ITツールは苦手」って人もすぐに使いこなせますよ♪
無料で登録できるので、ぜひ一度体感してみてください!


コメント