工事中にヘルメットは必要不可欠ですよね。
しかし、ヘルメットに関して詳しく理解している人は少ないのではないでしょうか。
着用時のルールや耐用年数、洗い方などをご紹介していきます!
工事現場ではヘルメット着用が義務
工事現場では、ヘルメットの着用が義務化されています。
労働安全衛生規則、クレーン等安全規則、行政指導通達による保護帽の着用規定など、それぞれで細かく着用規定が決められています。
上から物が降ってくる危険性がある場所、落下する危険がある場所での作業を行う場合は必ずヘルメットを着用するようにしましょう。
尚、厚生労働省は高さ1m未満の場所での作業であってもヘルメットの着用をすることを推奨しています。
というのも、建設業は転落による死亡事故が一番多い業種であり、ヘルメットを着用していなかったことが死亡の原因になっているからのようです。
自分の身を守るためにも、ヘルメットは必ず着用しましょう。
ヘルメットの役割は?
ご存じの通り、ヘルメットは危険な場所で作業する際に被るものです。
型式検定合格品には「労・検ラベル」が添付されており、そこには「飛来・落下用」「墜落時保護用」「電気用」と記載がありますが、それぞれ種類が異なります。
「飛来・落下用」とは、上から物が降ってくる危険、落下時の危険を防止・軽減するヘルメットのことです。
「墜落時保護用」とは、安全帯が使用できない場所からの落下による危険を防止するヘルメットのことです。
「電気用」とは、使用電力7000V以下で頭部感電による危険を防止するヘルメットのことです。

このように、ヘルメットは上から降ってくるものから頭を守るだけでなく、落下時や感電時の危険を防止する役割もあるのです。
軽作業帽との違い
軽作業帽とヘルメットを混同しがちですが、軽作業帽は布帽子に代わって頭の擦り傷などを防止する軽作業用の保護具です。
厚生労働省検定規格外のものなので、頭部の保護機能はほとんどないため、工事現場で着用するのは非常に危険です。
ヘルメット着用時のルール
工事現場で働く人を見ると、ヘルメットの色やラインの有無に違いがあったりしますよね。
これには意味があるのです。
尚、法律では色もラインについても特に規定はありません。
ラインについて
ヘルメットに入っているラインは、基本的にその人の役職を表しています。
【現場】
| ラインなし | 一般作業員 |
| 一本線 | 現場主任・工場長・役職者 |
| 二本線 | 現場管理人・現場監督・施工管理者 |
| 三本線 | 施工会社の重役 |
【会社】
| ラインなし | 一般作業員 |
| 一本線 | 班長・職長・現場リーダー |
| 二本線 | 社長・親方 |
会社によって多少の違いはありますが、基本的にはこのような違いのようです。
役職が上がるにつれラインが増えていくというイメージです。
色について
色についても、特に決まりがないので企業のイメージでカラーを付けているところもあります。
しかし、ヘルメットの色は白か黄色のイメージがありますよね。
多くの会社がヘルメットを白か黄色にしているのにも意味があります。
白色は光を吸収しにくいため熱を吸収しにくく、ヘルメット内の温度上昇を緩やかにする効果があります。
遠くからでも見つけやすく、光を反射するので夜間の工事でも目立ちやすいというメリットがあります。
清潔感があるというのもいい点です。
黄色は、どこからでも見つけられる色です。
遠くからでも暗い夜道でも黄色は目立つため、トラブルや事故に遭った時もすぐに見つけてもらうことができます。
また、山奥での作業中も周りに溶け込まず目立つため、はぐれたり事故が発生した時も見つけやすいです。
逆に山奥での作業で黒や緑のヘルメットは避けた方がいいです。
血液型について
ヘルメットに血液型を記載している人もいますが、血液型の記載は義務ではありません。
しかし、事故により輸血が必要となった際、血液型が一目で分かった方が対処が早くなるために社内規定として記載されていることがあるようです。
しかし、実際に輸血が必要となった場合は病院で血液検査を行うため、記載されていても意味はないらしいです。
もしかしたら、今後血液型の記載はなくなるかもしれませんね。
女性の場合は髪をヘルメット内にしまった方がいい
女性の場合、紙が長いとヘルメットを被っても外に出てしまいますよね。
長い髪が外に出ていると、機械に巻き込まれてしまったり、引っかかって転落事故に繋がる恐れがあります。
そうならないように、髪が長い場合はお団子にしたり三つ編みにして小さくして、ヘルメットの中に仕舞っておきましょう。
何かあってからでは遅いのです。
ヘルメットの耐用年数について
ヘルメットの耐用年数は、材質や使用状況によって異なります。
PC・ABS・PE等の熱可遡性樹脂製保護帽は、使用開始より3年以内。
FRP等の熱硬化性樹脂製保護帽は、使用開始より5年以内。
どちらも外観に異常がなくても交換してください。
ヘルメットの暑さ・寒さ対策
ヘルメットは夏と冬でそれぞれ困ることがあります。
対策方法を見ていきましょう。
夏で暑い場合
夏は、ヘルメットの中が熱で蒸れて被っていられないですよね。
その場合は、温度を下げてくれる冷感インナーキャップを被るのがおすすめです。
暑さだけでなく擦れも防げるので一石二鳥です。
その他の対策方法でいうと、
- 〇保冷剤とヘルメットと頭の間に入れる
- 〇ヘルメット用のファンを取り付ける
- 〇遮熱・通気孔付のヘルメットを使う
- 〇発砲七ロールなしのヘルメットを使う
このような暑さ対策があります。
冬で寒い場合
冬には、ヘルメット単体で作業を行うと寒い場合がありますよね。
そんな時は、暖かいメットカバーを被るといいでしょう。
裏起毛になっていて防風・防滴のものもあるので、冬でも快適に作業することができます。
それと一緒にネックウォーマーなどの首を保護できるものも使えば、顔を温めることができます。
ヘルメットの消臭
ヘルメットは夏も冬も被りますし、年単位で使うものなので使っていると臭いが気になってきますよね。
長年使うんだから清潔なヘルメットを被りたいはず!
そこでここでは、ヘルメットの洗い方などをご紹介します。
消臭スプレーを使う
菌がいなくなるわけではないので根本的な問題は解決できませんが、洗ったり乾かす時間がいらないので一番手間がかかりません。
尚、においが付いていると汗と混ざって臭くなる可能性があるため、無臭の除菌効果がある消臭スプレーを使いましょう。
天日干しをする
洗う時間がない場合は、被る面を一日中太陽に充てておきましょう。
消臭スプレーより雑菌を死滅させることができます。
汚れをふき取る
気になる部分をピンポイントに綺麗にすることができます。
全体を濡らすわけではないので、短時間で乾かすことができます。
【用意するもの】
- ・汚れたヘルメット
- ・キレイで柔らかい布
- ・中性洗剤
- ・水
- ➀水で薄めた中性洗剤を布にしみこませる
- ➁ヘルメットの内面や気になる部分を布で拭く
- ➂気になる部分をふき取れたら、布を洗って洗剤を落とす
- ➃ヘルメットの内側を水拭きする
- ➄風通しのいい日陰で干す
丸洗いする
一番きれいになる方法です。
- ➀バケツや桶に水を貯めてヘルメットを入れる
- ➁洗剤を投入して手洗いする
- ➂衝撃吸収材(発砲ライナー)がある場合、潰さないように丁寧に洗う
- ➃洗い終わったら綺麗な水ですすぐ
- ➄水を良く切って、風通しのいい日陰で干す
発砲ライナーが入っているヘルメットは、丸洗いする場合注意するべきことがあります。
- ・発砲ライナーは痛みやすいため優しく洗う
- ・発砲ライナの裏側はカビやすいので、水をよくふき取る
- ・ドライヤーは使わない
- ・有機溶剤は使わない
これらに注意して洗ってください。
快適に丸洗いするために、発砲ライナーがないヘルメットを使用するというのも一つの手です。
ヘルメットでもおしゃれを楽しめる!
ヘルメットはシンプルで一色だけで塗られているものがほとんどですが、色に規定がない分おしゃれにしたり企業カラーを出すこともできます。
ヘルメットがおしゃれなことで自分の仕事に誇りを持ったり、若者に興味を持ってもらうきっかけになるので企業ならではのおしゃれなヘルメットを用意するのもアリだと思います。
また、デザインがスタイリッシュでかっこいいものも出ています。
色にこだわりがない場合も、おしゃれにヘルメットを着用できます。
人気のかっこいい・オシャレなヘルメットを作っているメーカーをご紹介します。
進和化学工業

デザインがかっこよくちゃんと機能も備えているヘルメットを提供しているメーカーです。
カラーバリエーションも豊富で、迷ってしまうほどです。
夏用に通気孔ありのもの、冬用に遮熱式のものまで取り扱っており、様々な要望に応えてくれます。
マット加工やプリント加工もしてくれるので、企業独自のヘルメットを受注できます。
トーヨーセフティーメット

愛用者が多いトーヨーセフティーメットのヘルメット。
デザインのカッコよさだけでなく、機能性にも優れています。
通気性抜群のヘルメット「ベンティー」、携帯に便利な防災用ヘルメット「ムーボ」、防暑タレ付ヘルメット「ウインデ」など、工事現場の人が欲しいと思う機能を取り付けたヘルメットを販売しています。
タニザワ

シンプルでありながら必要な機能を備えた工事現場の人が使いやすいヘルメットを提供しています。
大型通気孔で夏も涼しく快適に被れるヘルメット、首の負担を軽減するため総重量たったの330gの超軽量ヘルメット、ひさしのある野球帽型ヘルメットは見た目が可愛いだけでなく、メンテナンスがしやすくなっているようです。
このように、実際の使いやすさを考えて作られているヘルメットが多いです。
まとめ
ヘルメットは工事現場で必要不可欠なものです。
だからこそ、正しい情報を入手して正しく着用しましょう。
今回の内容は、
・ヘルメットの着用は義務付けられている
・ヘルメットは、「飛来/落下用」「転落保護用」「電気用」の3種類がある
・高さ1m未満の場所であっても着用すべき
・色やラインに規定はないが、ラインは役職の違いで決まるのが一般的
・対応年数はモノによって違うが最大でも5年以内には交換しなければならない
このようにまとめられます。
ぜひ参考にしてください。
仕事・仲間を増やすならマッチングサービス「KIZUNA」!
KIZUNAは、建設業向けのビジネスマッチングサービスです。
仕事がほしい、職人が足りないといった悩みをネットで解決しませんか?
シンプルな掲示板で仕事の情報を掲載したり確認したりできるので、気軽にマッチングすることができます。
無料で登録できるので、ぜひ登録してください♪

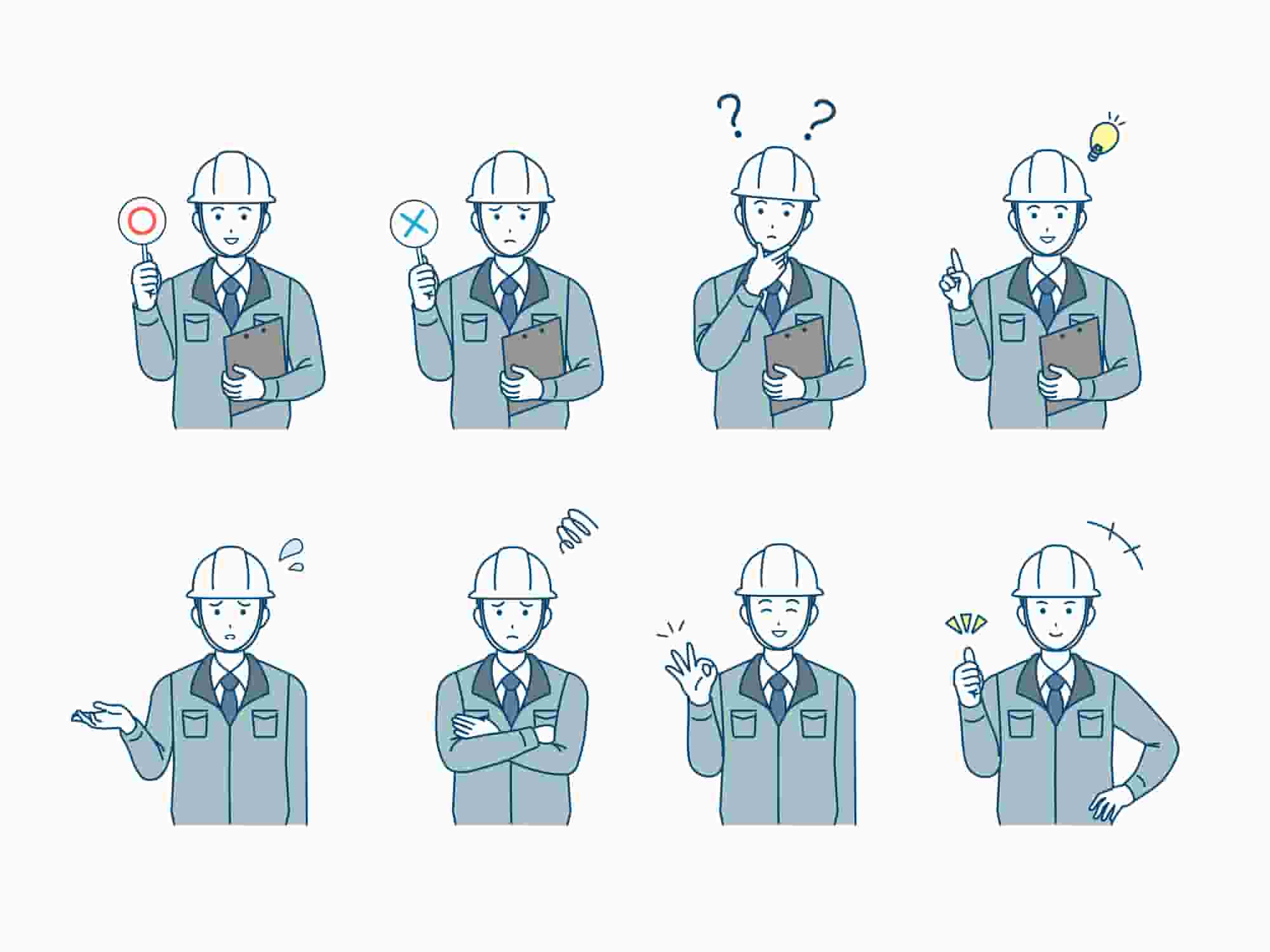
コメント