建設業者が仕事を行う際、遵守しなければいけないのが建設業法です。
建設業法を違反してしまうとどんな罰則があるのでしょうか。
事例を紹介しながら、罰則などを紹介していきたいと思います。
建設業法とは?

建設業法とは、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化を図ることにより、
- 建設工事の適切な施工を確保
- 発注者の保護
- 建設業の健全な発展の促進
- 公共福祉の増進に寄与する
上記の実現を目的に定められたものです。
建設業法は、戦後復旧による建設ラッシュで建設業者が急増し、競争状態になったことで低品質の施工・代金未払い・ダンピング受注(不当に安い金額で適正な施工が見込まれない契約)などが横行したため、それをなくし適切な施工が行われるように制定されました。
その後、建設業の慢性的な人手不足から、労働条件の改善やルールの合理化、生産性向上のために2020年、2022年に改正されました。
このように、建設業の不正をなくすために制定された法律なので、違反すると大きな罰則が科されます。
一体どのような行為が違反行為なのか、次の項目では違反事例を見ていきましょう。
建設業法の違反事例を紹介

違反行為となる行動はいろいろなケースがあるので、その中の一部を紹介したいと思います。
定められた金額を超えた契約を交わした
建設業者は、1件の工事請負金額が500万円以上の工事を請け負う場合は建設業許可が必要になります。
建設業許可の中にも「一般建設業許可」と「特定建設業許可」があり、1件の工事請負金額が500万円以上4500万円未満の場合は「一般建設業許可」、4500万円以上の場合は「特定建設業許可」が必要です。
建設業許可を取得していないのに、請け負える金額以上の工事を受注してしまった場合、建設業法違反になってしまいます。
虚偽申告をした
過去に変更事項があったにも関わらず、届出をしないまま許可を申請することは違反に該当します。
また、見積もり依頼に関して、口頭でのみ指示を行い書面に提示しない、工事種別ごとの材料費等の経費内訳を明記せず一式という表記で記載している、など、書面での報告に不備がある場合も罰則の対象となります。
技術者などの配置義務違反
通常、工事現場ごとに専任の主任技術者または監理技術者を配置しなければいけません。
しかし、人手が足りないなどの理由で営業所の専任技術者が配置されていたり、要件を満たさない技術者が配置されていたりと、専任ではない技術者の配置、配置を怠った場合は罰則の対象となります。
一括下請負を行った
一括下請負とは、元請け業者が、受注した工事を下請け業者に丸投げすることです。
元請けが工事に一切関与しないで利益を得ようとする行為であり、下請け業者に適切な報酬が支払われなかったり、工事の質が下がったりする可能性があります。
適切な工事が行われない原因となるので、罰則対象です。
下請け業者への報酬の未払い
発注者からの支払いを元請け業者が受け取っているにも関わらず、1カ月以上下請け業者に報酬を支払わない場合は違反になります。
元請け業者は、下請け業者にできるだけ早く報酬を支払う義務があります。
廃棄物処理法違反
建設業の業務に関連するものの不法投棄や野焼きなどを行い、役職員が廃棄物処理法違反により処罰された場合、監督処分の対象となります。
役員が刑法違反や暴力団だった
役員が暴行や詐欺などの理由で懲役刑が決定した場合や、暴力団員でなくなってから5年を経過していない役員がいた場合、建設業許可が取り消されてしまいます。

これらは違反行為の一部ですが、不正や適切な工事が行われない可能性がある場合は違反になると思ってください。
また、元請け業者は下請け業者に指示を出すなど立場が上なので、下請け業者が不利になるようなことをやる、不正を黙認するなどした場合は責任を取る必要があります。
その部分をよく理解し、適切な工事が行われるように注意していきましょう。
違反した場合の罰則や監督処分について

違反した場合、罰則や監督処分を受けることとなります。
どのような内容なのか見ていきましょう。
罰則
10万円以下の過料
義務違反など、比較的軽微な違反の場合に科されます。
- 廃業などの手続きを怠った(30日以内に届け出をしなかった等)
- 無許可業者が建設業許可を取得していると誤認される表示をした
- 現場の標識を掲載しなかった
- 帳簿の不備や虚偽の記載をした
100万円以下の罰金
不正をしようとした場合などに科されます。
- 工事現場に適切な技術者を設置しなかった
- 監督処分を受けた際、その旨を発注者に通知しなかった
- 国土交通大臣や行政庁による検査や立ち入りを拒否
- 経営状況分析に必要な書類を提出しない、虚偽の報告をした
- 適切な許可を得た下請け業者に施工をさせなかった
6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金
主に届出書の記載に虚偽の報告があった場合に科されます。
- 建設業許可申請書に虚偽の申告をした
- 経営状況分析申請に虚偽の記載をして提出した
- 変更届の提出を怠った
- 建設業の不許可事由に該当した際、その届出をしなかった
3年以下の懲役または300万円以下の罰金
建設業法違反の中で最も重い罪を犯した場合に科される罰則です。
- 建設業許可を受けないで許可のいる工事を行った
- 特定建設業者でない者が、法定金額以上の工事を契約した
- 営業停止処分に違反して営業を続けた
- 虚偽または正当でない方法で許可を受けた
場合によっては、懲役と罰金の両方が科されることもあります。
監督処分
指示処分
監督処分の中で最も軽い処罰で、誤って行ってしまった場合や初めての場合は行政庁からの指示処分となります。
今後、建設業法違反や不適切な行動を起こさないように、具体的な改善命令が指示されます。
営業停止処分
指示処分に従わない場合、営業停止処分となります。
営業停止期間は、監督行政庁によって1年以内の期間で決められます。
営業停止の範囲は、違反内容によって全て停止か一部停止か決められます。
一括下請負禁止規定違反、独占禁止法や刑法など、他の法令に違反した場合は指示処分を飛ばして営業停止処分になる可能性があります。
営業停止中でも、次のような行為は行うことができます。
- 建設業許可や経営事項審査などの申請
- 営業停止処分前に締結した工事の施工
- アフターサービス補償に基づく修繕等の施工
- 災害時の緊急を要する施工
- 請負代金の請求、支払い
- 企業運営のために必要な資金の借り入れ
新しい工事の受注や停止前に受注していた工事の追加などは行ってはいけません。
建設業法違反を犯すと、5年間は建設業許可を取得できなくなる
正当でない方法で建設業許可を取得した場合や指示処分や営業停止処分に違反した場合は、その後5年間は新しく建設業許可を取得できません。
建設業許可を取得できないと、500万円以下の簡単な工事しかできないので、できる仕事の範囲が減って売上も著しく減少してしまいます。
企業の存続にも関わるので、絶対に建設業法に違反しないよう、適切な環境での施工を心がけてください。
違反を告発する場合、どこに通報すればいいのか

万が一、自分が働いている建設会社や下請け業者で違反が発覚した際、どこに相談すればいいか悩みますよね。
その際は、
- 建設業法違反通報窓口(駆け込みホットライン)
- 各都道府県の許可行政庁
上記のどちらかに連絡しましょう。
【建設業法違反通報窓口(駆け込みホットライン)】
- 電話番号:0570-018-240
- FAX:0570-018-241
- メールアドレス:hqt-k-kakekomi-hl@gxb.mlit.go.jp
- 受付時間:10:00~12:00/13:30~17:00(土日・祝日・閉庁日を除く)
【各都道府県の許可行政庁】
建設業者の許可行政庁を確認する場合はこちら
各許可行政庁の連絡先はこちら
違反のない健全な工事を行おう!
違反してしまうと大きな罰則がありますし、施工現場の安全性も脅かされてしまいます。
安全で高品質な建物を建てるには、従業員が満足できる環境を整えることが重要です。
建設業法を遵守して、安全な現場を作っていきましょう。
建設業向けマッチングサービスなら「KIZUNA」
「人手が足りない」
「協力会社とのつながりを増やしたい」
そのようなお悩みがある建設業者の方必見!!
建設業向けマッチングサービス「KIZUNA」で、そのお悩みを解決できます♪
完全審査制、安心のサポート体制、見やすい掲示板で、安心安全にビジネスマッチングしてみませんか?
無料登録できるので、まずは使い勝手を体験してみてください!

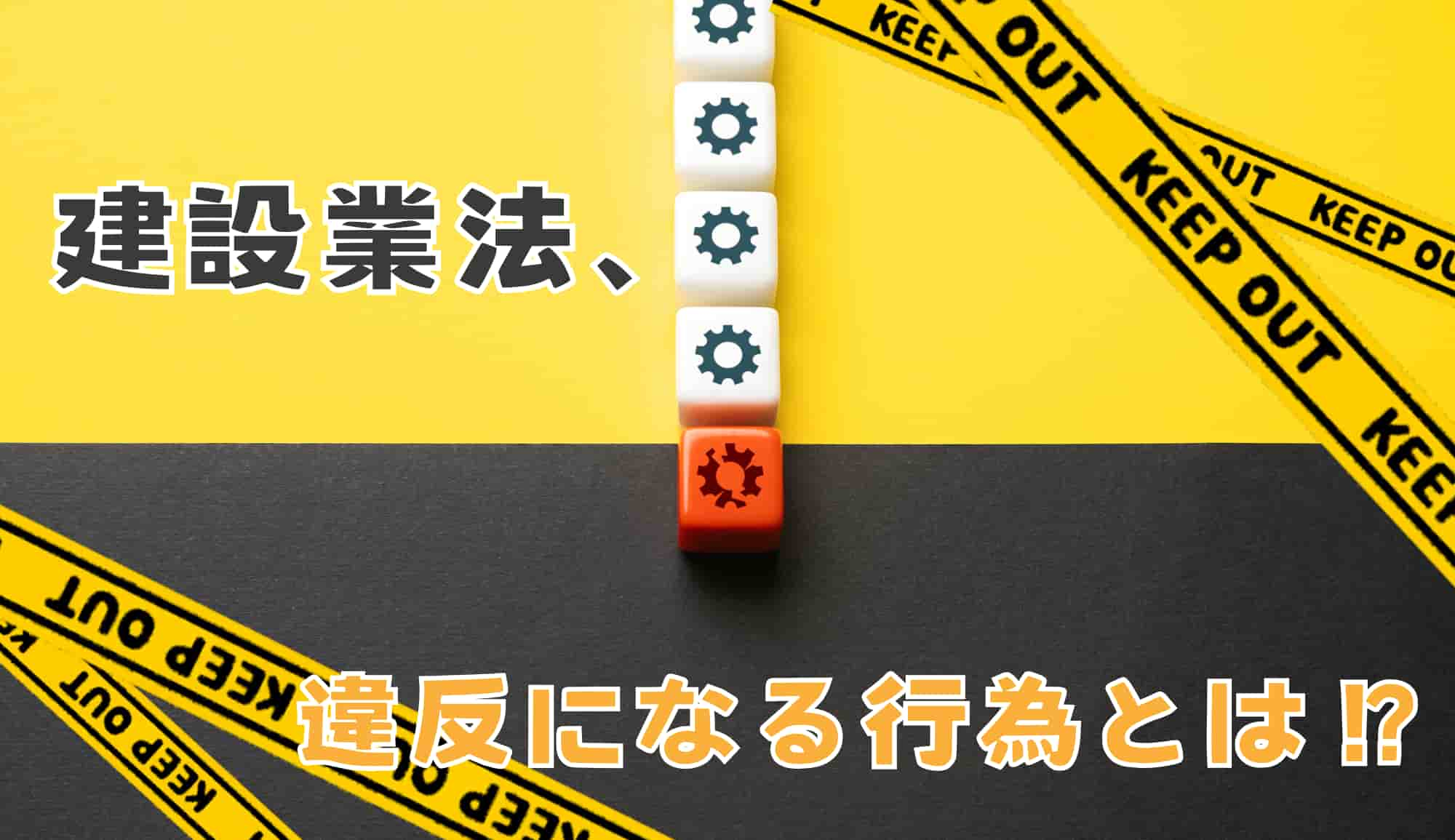
コメント