2024年4月から、建設業でも時間外労働の上限規制が適用されます。
長時間労働が当たり前の建設業で残業を減らすためには、従業員の勤怠管理が必須になります。
そこで今回は、建設業における勤怠管理の必要性や課題を伝えつつ、おすすめの勤怠管理システムを紹介していこうと思います。
建設業では勤怠管理があやふやなところが多い
建設業は事務所より現場で過ごす時間が多いため、直行直帰になる確率が高いです。
タイムカードで管理している場合、事務所でタイムカードを押すことができないためしっかりした勤怠管理ができません。
後で手書き入力してもらっても、正確に時間を把握しているとは限らないため勤務時間を正確に管理できているとはいえませんよね。
2023年9月に勤怠管理ツールを提供するJingerが建設業に向けて行ったアンケート調査を見てみましょう。

画像出典元:Jinger
「どのような方法で労働時間を集計していますか?」という質問に対し、「タイムカードやExcel」と回答したのが約25%、「日報等による従業員の自己申告」と回答したのが29.3%でした。
このように、アナログな管理方法をとっている建設企業が多いのが現状です。
2024年の時間外労働の上限規制に対応するためにも、もっとしっかりした勤怠管理を行う必要があります。
なぜ勤怠管理が必要なの?
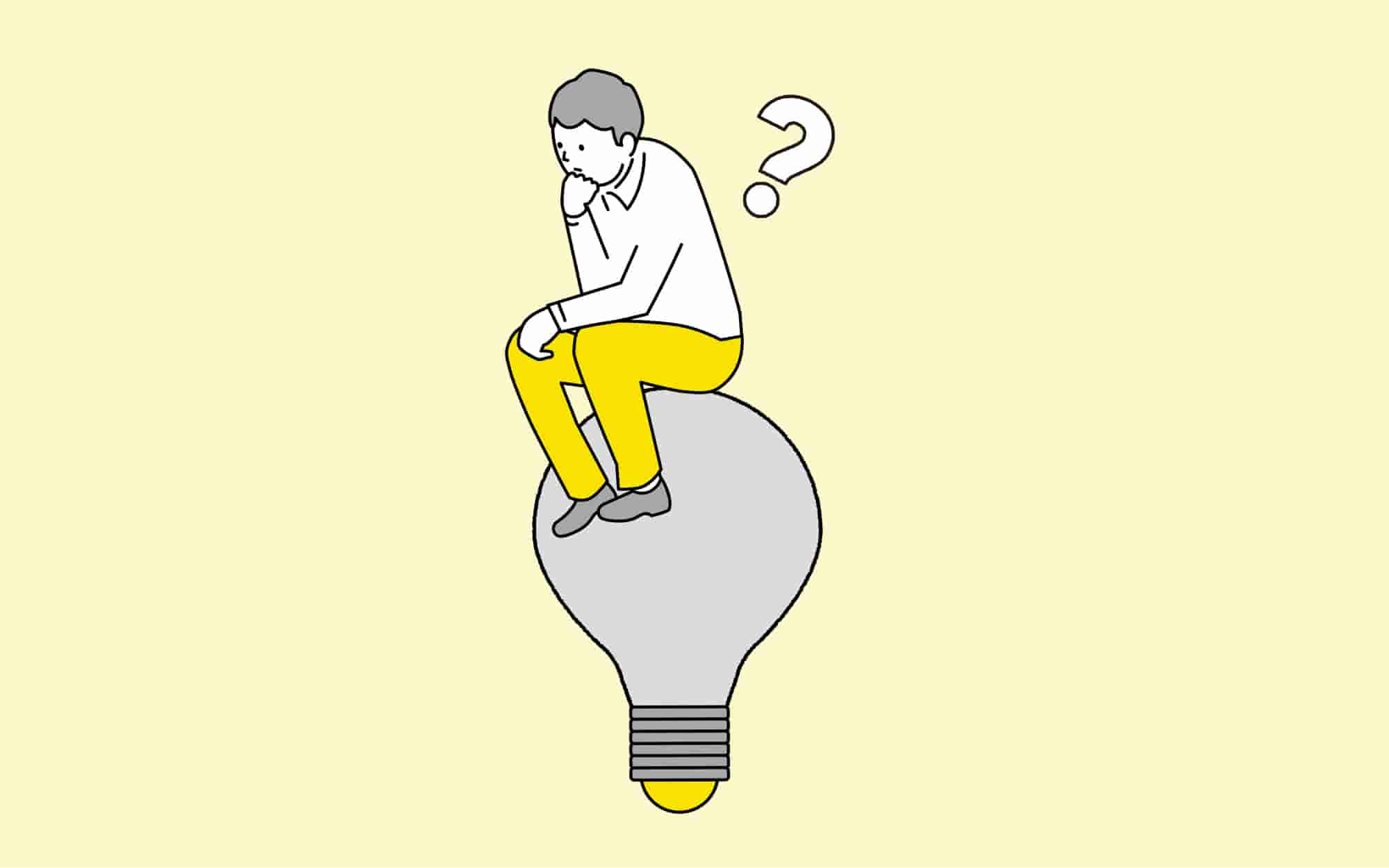
そもそも、なぜ勤怠管理が必要なのでしょうか。
勤怠管理をすることで、
- 従業員の勤怠時間を正確に把握できる
- 正しい給与計算ができる
- 企業の健全な就業環境を守る
などのメリットがあります。
詳しく説明していきましょう。
従業員の勤怠時間を正確に把握できる
従業員の労働時間を正確に把握することができるため、長時間労働を防ぐことができます。
通常の労働時間はもちろん、休日出勤や有休取得数なども把握できるようになるため、従業員の健康管理にも繋がります。
正しい給与計算ができる
正確な勤怠管理を行うことで、勤務時間に合った正しい給与計算が可能になります。
特に残業代は、合計時間によっては基本給に加えて支払う必要があるため正確に把握する必要があります。
従業員が納得のいく給与を支払うためにも、正確な勤怠管理が必要なのです。
企業の健全な就業環境を守る
勤怠管理が正確でないと、残業時間を少なく見積もったりタイムカードを切った後に残業をさせたりするブラック企業が蔓延ってしまいます。
適切な勤怠管理を行うことで、不当な残業をなくし従業員の健全な就労に繋がるのです。
タイムカードがない場合は違法?
タイムカードは、従業員が出退勤をする際にその時刻を書き込む用紙のことです。
タイムレコーダーに差し込むと自動で勤務時間を記入してくれます。
タイムカードがなくても他の方法で勤怠管理をしていれば違法にはなりません。
しかし、勤怠管理をしていないと違法になるので注意が必要です。
従業員の労働時間の把握は2019年に改正された労働基準法によって義務化されました
労働時間を記録した書類を5年間保管する、休日や就業時間などを賃金台帳に適正に記録する、労働時間の客観的な把握義務などが法律で定められているため、従業員の勤務時間を把握していなければこれらもできていないとみなされて違反になってしまいます。
違反すると罰則が科せられますので注意してください。
要確認!建設業における勤怠管理の課題

建設業では、勤怠管理にどんな課題を抱えているのでしょうか。
課題を把握して、自社の勤怠管理を見直すきっかけにしてください。
直行直帰が多い
上記でも記載したように、建設業は現場で働くため直行直帰が多いです。
タイムカードの勤怠管理では、直行直帰をする従業員の勤務時間を正確に把握することができません。
後から手書きで書いてもらうことになるので、勤務時間もあいまいになってしまいます。
アナログな管理をしているところが多い
上記のアンケート調査の結果をみても分かるように、建設業では勤怠をアナログな方法で管理しているところがほとんどです。
そのため、従業員の自己申告で勤務時間を集計している企業も多く、正確な勤怠管理ができていません。
従業員の勤怠状況が複雑
建設業は人手不足が深刻なため、能力のある従業員は複数の現場を掛け持ちしていることも珍しくありません。
現場によって勤務時間や休日が異なるため、集計が複雑になります。
そのような状況で勤怠管理方法がタイムカードだと、一気に勤怠報告をする従業員も出てきて管理者の負担が大きくなってしまいます。
従業員の自己申告なので情報の信頼性も低く、適切な労働環境を整えることができないのです。
勤怠管理の重要性が浸透していない
建設業において、勤怠管理の重要性が浸透しておらず、「とりあえず付けておくか」くらいで考えている企業も少なくないのではないでしょうか。
今はそれで不自由がないかもしれませんが、長時間労働の上限規制が始まったら適正な勤怠管理をしなければいけなくなります。
今のうちに適正な勤怠管理をする準備を整えていきましょう。
勤怠管理システムを導入するメリット
勤怠管理を正確に把握するなら勤怠管理システムを導入するのがおすすめです。
なぜおすすめなのか、勤怠管理システムのメリットを見ていきましょう。
場所に関係なく打刻できる
勤怠管理システムはGPS機能を搭載していてスマートフォンやアイパッドなどのマルチデバイスからも打刻できます。
GPS機能によっていつ、どこで打刻したのかが分かるようになっているのです。
直行直帰が多く現場も変わりやすい建設業にとって、場所に関係なく打刻ができるのは一番のメリットですよね。
勤怠管理の負担を減らすことができる
場所関係なく打刻をしてもらえるので、打刻忘れが減り正確な勤怠管理ができます。
また、従業員の勤務時間をデータ化し自動集計してくれるので、管理の負担を減らすことができます。
勤務時間をリアルタイムで把握できる
リアルタイムで勤務時間を把握できるので、長時間労働がないか、休日はしっかりとれているかなども確認できます。
これにより、従業員の健康管理にも気を遣うことができて過労死や鬱などを防止することができます。
法改正に対応できる
労働の基準値を設定することで超過した時にアラートがなるようになっている勤怠管理システムもあるので、2024年の長時間労働の上限規制にも対応できます。
建設業においてこの法改正がネックになってくると思うので、勤怠管理システムを導入することで強制的に長時間労働を減らすことが可能になります。
シフト管理もできる
勤怠管理システムでは、シフト管理機能がついているものも多いです。
複数の現場が同時に動いている場合でも、誰がどの現場で働いているかをすぐに確認できるためシフト管理が楽になります。
シフトを把握して労働時間に合わせて人数調整をするなどができるので、長時間労働を防ぐことができます。

このように、勤怠管理システムは建設業の問題を解決する機能を多く備えています。
コストはかかりますが、どの分メリットが大きいので導入することをおすすめします。
これがおすすめ♪勤怠管理システムの選び方
勤怠管理システムはたくさんあるので、どれにすればいいか迷いますよね。
ここでは、勤怠管理システムの選び方を紹介していこうと思います。
ぜひ参考にしてください。
必要な機能が備わっているか
まずは勤怠管理システムでどんな課題を解決したいかを明確にし、それを解決する機能を備えたシステムを選ぶようにしましょう。
たくさんの機能を搭載しているものもありますが、欲しい機能が付いていなければ意味がありません。
欲しい機能をピックアップして、それが付いているかを基準に選ぶようにしましょう。
シンプルで使いやすか
長く使っていくものになるので、使いやすさも重要です。
従業員全員がすぐに使いこなせて管理者の負担も減らせるような、シンプルで見やすい操作・画面のものを選びましょう。
建設業は若い人が少ない分ITツールに疎い方も多いと思うので、誰でも使いこなせるシンプルさが必要になります。
使っているシステムを連携できるか
給与計算・労務管理など既に使っているシステムがあるならそれらと連携できるかも確認してください。
システムと連携できればより効率よく管理ができるようになり、管理者の負担を削減できます。
さらに、既存システムと連携できるものであれば新しくシステムを入れるコストを削減することにも繋がります。
法改正に対応する機能があるか
上記でも紹介した長時間労働のアラート機能や有給休暇取得状況の把握機能など、法令順守をサポートしてくれる機能があるかも確認しましょう。
法令は頻繁に改正されるため、自動更新で対応してくれるシステムがおすすめです。
費用が予算内に収まっているか
欲しい機能が備わっていても、かかる費用が高額すぎたら利用を続けていけませんよね。
まずは勤怠管理システムにかける予算を決めて、その予算に収まるかどうかも判断基準にしてください。
月額制のシステムが多いので、1か月にかかる費用で比較してみてください。
サポートが充実しているか
勤怠管理システムに限らず、システムを利用していくのにサポートの充実度は外せない部分です。
何かトラブルが起きたり機能面で分からないことがあったりした時にすぐ対応してもらえる方がいいですよね。
チャットやメール対応だけでなく、電話対応もしている方が安心できます。
セキュリティ体制はしっかりしているか
勤怠管理システムはクラウド型なので、セキュリティ体制がしっかりしていないと情報漏洩やウイルス感染の恐れがあります。
クラウド型の場合はベンダー側の対策状況でセキュリティのレベルが異なるので、導入前にしっかり確認しましょう。
打刻方法はどんなものがあるか
勤怠管理システムにはPC打刻やモバイルGPS打刻だけでなく、指紋認証打刻・ICカード打刻・顔認証打刻など様々な打刻方法があります。
なりすましや不正打刻を防ぎたい場合は指紋認証や顔認証打刻がおすすめですが、これは場所が限られてしまうためオフィス勤務の少ない建設業には向いていません。
このように、打刻方法が多くても向き不向きがあるので、どれが一番勤務形態に向いているか考えてシステムを選ぶのがいいです。
評判はいいか
実際に導入した企業の評判も気になりますよね。
どういうところが良くてどういう課題があるのか参考になるので、ぜひ評判は確認してほしいです。
しかし、その中にはやらせや個人の感情で話を盛って書いている場合もあるので、あくまで参考程度にしてください。
無料トライアルはできるか
無料トライアルや無料プランがあるか確認しましょう。
無料でお試し利用できれば機能や使い勝手が分かり、従業員にとっても使いやすいものかどうかを判断した上で導入することができます。
無料トライアルや無料プランがある場合はぜひ利用してみてください。
おすすめの勤怠管理システム3選
では、オフィ助がおすすめする勤怠管理システムを3つ紹介します。
ぜひ参考にしていってください。
キングオブタイム

利用者307万人突破の勤怠管理システム。
-
・打刻方法が豊富
・有休管理、アラート管理、働き方改革関連法の設定など法改正に対応
・シンプルな画面
・万全のセキュリティ
・豊富な外部連携
・電話・チャット・メールでのサポート(無料プランの電話は予約制)
・無料体験あり(30日)
初期費用:0円 月額費用:300円
キングオブタイムについて詳しくはこちらの記事で紹介しているので、一緒にご覧ください♪
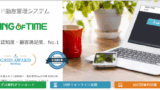
ジョブカン

2022年度のITトレンド年間ランキング1位を獲得している勤怠管理システム。
・複数拠点での勤怠管理
・打刻忘れ防止機能がある
・アラート機能で長時間労働防止
・外国語に対応(英語・韓国語・スペイン語)
・電話・チャット・メールでのサポート
・無料体験あり(30日)
初期費用:0円 月額費用:200円~(機能数により変動)
ダイナクラウド勤怠

シャープが提供している勤怠管理システム。
・シフト管理、残業管理、休暇管理機能も使える
・追加費用無しで導入
・運用サポートがある
・法改正に対応
・万全のセキュリティ
・無料体験あり(30日)
初期費用:0円 月額費用:300円
勤怠管理システムもKIZUNAにお任せ!
このように、建設業の勤怠環境を改善するためには勤怠管理システムの導入がおすすめです。
KIZUNAでは、上記で紹介したキングオブタイムとダイナクラウド勤怠を取り扱っています!
システムについての軽い質問だけでも構いません。
気になることが少しでもあれば、ぜひお気軽にご連絡ください♪


コメント