さまざまな建物を設計し、世の中に自分が設計した建物を残すことができる「建築士」。
建設業に興味がある人は、建築士に憧れ目指す人が多くいると思います。
建築士になるにはどうすればいいのか、必要な資格や学校の選び方などを紹介していきたいと思います。
建築士とは

建築士を簡単に説明すると、店舗やオフィス・一般住宅の設計図を作成したり、施工監理をしたりする人のことです。
建築士になればさまざまな建物を設計できるので、世の中に自分が作った建物を残すことができます。
建築士の種類
建築士は「一級建築士」「二級建築士」「木造建築士」の3種類に分かれています。
それぞれ扱える建造物の規模や種類が異なるため、3種類のうちどれに進んでいくか決める必要があります。
一級建築士
国土交通大臣の免許を受け、建物の設計・施工監理の業務を行います。
一般住宅はもちろんですが、劇場やスタジアム、学校などの大型建設物を設計できるのは一級建築士だけです。
できる仕事の幅がかなり広いため、資格手当や昇給に繋がりやすいです。
ビジネスチャンスも多く、独立時にも高く評価されるでしょう。
【扱える建物の範囲】
- ◎学校や病院などの用途に供する建築物で、延べ面積が500㎡を超えるもの
- ◎高さ13m(3階建て)または軒の高さが9mを超える木造建築
- ◎鉄筋コンクリート・鉄骨造等の建物で、延べ面積300㎡、高さが13m(3階建て)または軒の高さが9mを超えるもの
- ◎用途・構造に関わらず、延べ面積が1000㎡を超え、かつ階数が2階以上の建物
二級建築士
都道府県知事の免許を受け、一般住宅の設計や工事管理を行います。
一級建築士に比べて扱える建築物の範囲は制限されますが、ほとんどの戸建て住宅に携わることができます。
【扱える建物の範囲】
- ◎延べ面積が30㎡を超え300㎡以内のもの
- ◎延べ面積が100㎡(木造建築物の場合は300㎡)を超え、または階数が3階以上のもの
木造建築士
都道府県知事の免許を受け、木造の建築物を設計・施工監理を行います。
近年エコに対する意識が上がり、素材を生かした建築物の需要が高まっているため、木造建築士の注目度も大手建設業を中心に上がっています。
設計・管理が可能な建物に制限がありますが、伝統的な木材などの専門知識を有するため神社仏閣などの伝統的建築物、歴史的建造物の修繕・維持に携わることができます。
【扱える建物の範囲】
- ◎2階建て以下の木造建築物で、延べ面積が100㎡を超え300㎡以内のもの
設計士との違い
建築士と混合されがちなのが「設計士」という仕事です。
建築士と設計士の一番の違いは資格があるかどうかです。
建築士は一級・二級・木造の資格がそれぞれあり、それを有している人を建築士と呼びます。
一方、設計士は必要な資格はなく、主な仕事は設計の補助や限られた建築物の設計になります。
建築士の資格を持たない設計士でも設計できる建築物の条件は以下になります。
- ・100㎡未満の木造建築物
- ・30㎡未満、高さ13mかつ軒の高さが9m以下の建築物
仕事内容

建築士の主な仕事内容はどんなものか見ていきましょう。
クライアントとの打ち合わせ
どのような建物を建ててほしいのか、クライアントと打ち合わせを行います。
建物の用途やイメージ・構造・収容人数など、設計に必要な情報をヒアリングしてお互いに意見のすり合わせを行います。
設計
建物の構造・設備・外装・内装などが決まったら、ヒアリング内容を基に建物の設計図や仕様書を作成します。
もちろん、法律を遵守した設計図を作成します。
設計作業は、建物の安全性を考えて骨組みを考える「構造設計」、空気・電気・水道などのインフラを考える「設備設計」、内装や間取りなどデザインを考える「意匠設計」に分けられます。
大手企業の場合は、これらの設計業務を分担して専門的に行う場合もあるようです。
施工監理
設計図や仕様書が完成したら、クライアントに見てもらい了承をもらいます。
その後は、設計図通りに建物を造ってもらうために、現場監督や施工監理の方とやり取りをしながら、工事の進捗状況を確認します。
設計図通りに施工が行われているかを目視で確認し、現場の方と話し合って途中で設計を変更することもあるようです。
それに加えて、クライアントへの報告も建築士の仕事になります。
その他事務作業
建設業許可、道路使用許可、行政手続きなどの事務作業も行います。
建築士になるにはどうすればいい?

必要な資格
一級建築士
建設業希望の学生の多くが取得を目指す資格です。
関われる建築物の範囲が広いため、より多くの設計に携わることができます。
取得後のメリットが大きい分、3種類の中で一番資格取得が難しいです。
しかし、令和2年から受験資格が緩和され実務経験が必要なくなったため、以前よりも一級建築士に挑戦しやすくなっています。
【資格要件】
- ・4年生大学/短期大学/高等専門学校で指定科目を修めて卒業
- ・二級建築士の資格を持っている
- ・建築設備士の資格を持っている
- ・その他国土交通大臣が特に認める者(外国大学卒業者等)
【必要書類】
- 顔写真の電子ファイル(全員)
- 平成20年以前入学の場合:卒業証明書
- 平成21年以降入学の場合:指定科目修得単位証明書・卒業証明書
- 二級建築士:二級建築士免許証の写し
- 建築設備士:建築設備士資格合格証明書
【試験料】
- 17000円+その他事務手数料
【申込方法】
- 原則インターネットによる受付のみのため、受験申込書の配布はなし。
- インターネットでの申し込みが行えない理由がある場合は、お問い合わせが必要です。
【必要勉強時間】
一級建築士の合格率は低く、平均12%ほどです。
受験者9割が不合格となるほど難関資格なので、かなりの勉強量が必要になります。
一般的に1000時間を勉強に費やさないといけないと言われており、一日の3時間の勉強が必要になります。
もちろんそれよりも少ない勉強時間で合格している人もいますので、実際に一級建築士の資格を取った人のブログを参考にするといいでしょう。
二級建築士
一級建築士よりも関われる建築物の範囲は制限されますが、ほとんどの建築物の設計に携わることができます。
一級建築士よりも資格の合格率が高いため、二級建築士を目指す人も多いでしょう。
また、二級建築士の資格を取ることで一級建築士の受験資格を得られるので、それを目的に受験する人もいるようです。
二級建築士の受験資格も緩和され、実務経験の項目がなくなり受験しやすくなっています。
【受験資格】
- ・4年生大学/短期大学/高等専門学校/専修学校/職業訓練校等で指定科目を修めて卒業
- ・建築設備士
- ・その他国土交通大臣が特に認める者(外国大学卒業者等):所定年数の実務経験
- ・建築に関する学歴なし:実務経験7年以上
【必要書類】
- 顔写真の電子ファイル(全員)
- 平成20年以前入学の場合:卒業証明書
- 平成21年以降入学の場合:指定科目修得単位証明書・卒業証明書
- 二級建築士:二級建築士免許証の写し
- 建築設備士:建築設備士資格合格証明書
【試験料】
18500円+事務手数料
【申込方法】
- 原則インターネットによる受付のみのため、受験申込書の配布はなし。
- インターネットでの申し込みが行えない理由がある場合は、お問い合わせが必要です。
【必要勉強時間】
二級建築士の合格率は平均24.7%です。
一級建築士よりは合格率が高いですが、国家資格の中では取得が難しい資格です。
勉強時間の目安は700時間で、1日2時間ほどの勉強が必要です。
二級建築士の資格は合格点が60点以上とそこまで高くないため、独学で取得している人も多いようです。
木造建築士
木造建築士は、二級建築士よりも関われる建築物の範囲が狭く、合格率も比較的高いです。
受験資格は二級建築士と同じで、実務経験7年以上があれば学歴がなくても受験できます。
伝統的建築物、歴史的建造物の修繕などに関わりたい方は取得することをおすすめします。
【受験資格】
- ・4年生大学/短期大学/高等専門学校/専修学校/職業訓練校等で指定科目を修めて卒業
- ・建築設備士
- ・その他国土交通大臣が特に認める者(外国大学卒業者等):所定年数の実務経験
- ・建築に関する学歴なし:実務経験7年以上
【必要書類】
- 顔写真の電子ファイル(全員)
- 平成20年以前入学の場合:卒業証明書
- 平成21年以降入学の場合:指定科目修得単位証明書・卒業証明書
- 二級建築士:二級建築士免許証の写し
- 建築設備士:建築設備士資格合格証明書
【試験料】
18500円+事務手数料
【申込方法】
- 原則インターネットによる受付のみのため、受験申込書の配布はなし。
- インターネットでの申し込みが行えない理由がある場合は、お問い合わせが必要です。
【必要勉強時間】
試験は学科と製図があり、総合の合格率は平均36%です。
一級や二級と比べると合格率は高く、難易度はそこまで高くないです。
一般的に必要な勉強時間は300~400時間と言われており、独学でも十分取得できる資格のようです。
建築士になるためのステップ
一級建築士を目指すときの進学の流れを見ていきましょう。
一級建築士になる勉強をする
↓
一級建築士の受験資格を得る
↓
一級建築士の試験に合格する
↓
必要な実務経験を積む
↓
一級建築士として登録する
大まかな流れはこのようになります。
必ずしも大学や専門学校に入る必要がないので省いています。
まずは一級建築士の受験資格を得る必要があるので、
- 大学・専門学校に通い指定科目の単位を取得する
- 二級建築士の資格をとる
- 建築設備士の資格をとる
このどれかを選ぶことになります。
①大学・専門学校に通い、指定科目の単位を取得する
指定科目の単位を取得して卒業することで、一級建築士の受験資格を得ることができます。
大学、専門学校における指定科目は以下のものです。
建築設計製図(7単位)
建築計画(7単位)
建築環境工学(2単位)
建築設備(2単位)
➁二級建築士の資格をとる
二級建築士の資格をとることで、一級建築士の受験資格を得ることができます。
二級建築士の受験資格は上記でも紹介したとおり、
- ・4年生大学/短期大学/高等専門学校/専修学校/職業訓練校等で指定科目を修めて卒業
- ・建築設備士
- ・その他国土交通大臣が特に認める者(外国大学卒業者等):所定年数の実務経験
- ・建築に関する学歴なし:実務経験7年以上
のいずれかです。
学校に行っていなくても実務経験が7年以上あれば受験できるので、学歴がなくても受験できます。
③建築設備士の資格をとる
建築設備士の資格をとることで、一級建築士の受験資格を得ることができます。
建築設備士の受験資格は以下です。
- ・大学卒業後、実務経験2年以上
- ・短期大学、高等専門学校卒業後、実務経験4年以上
- ・高等学校卒業後、実務経験6年以上
- ・一級建築士、一級電気工事施工管理技士など、実務経験2年以上の資格者
- ・建築設備に関する実務の経験のみの者は実務経験9年以上
実務経験重視ですが、年数が多いので実務未経験の方には難しいかと思います。
以上から、学校に通って指定科目の単位を取得するのが一番の近道といえます。
【年齢別】建築士になるための最短コース
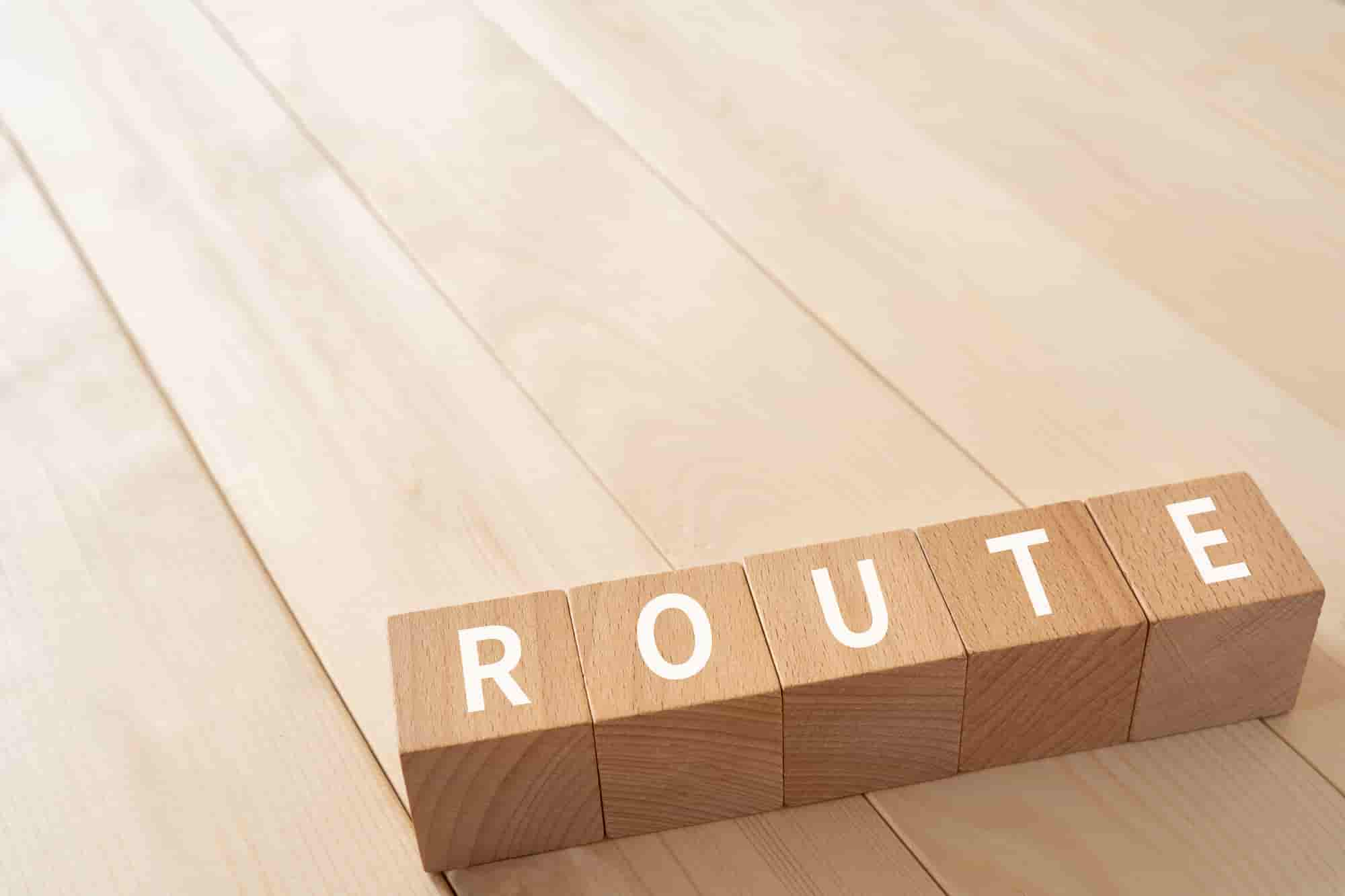
若くから目指し始めた方が選択肢は多いですが、社会人からだって建築士を目指すことはできます!
ここでは、建築士になるための最短コースを年齢別でみていきましょう。
中学生
中学生から一級建築士を目指す場合、多くの選択肢から道を選ぶことができます。
大学や専門学校に入ることを考えているのなら、そのための基礎知識を習得するために勉強をしていい成績をとっておきましょう。
建築士は設計図を描くので、設計図というのはどういうものか触れておくといいと思います。
設計図の本はたくさん出ているので、中学生でも見やすいものを購入してみてください。
また、建築士はさまざまな建物を設計するので、今のうちからいろんな建物を実際に見ておきましょう。
実物をたくさん見ることで想像力も育めますし、「建物を造る」というイメージが沸きやすくなるかと思います。
なお、進学する高校は建築科や土木科があるところを選ぶのがおすすめですが、最短ルートは中学卒業後、高等専門学校に通う方法です。
高等専門学校は工業高校と工業大学を掛け合わせたような学校であり、5年間で建設業関連の勉強をスピーディに行ってくれます。
早くから専門的な知識を学べる上に、就職サポートも充実しているようです。
卒業と同時に二級建築士・一級建築士の受験資格を得ることができるのもメリットです。
流れとしては以下を参考にしてください。
【二級・木造建築士の場合】
中学卒業(15歳)→高等専門学校入学(5年)→卒業後試験を受ける(20歳)→資格取得し、建築士として登録する(20歳)
【一級建築士の場合】
中学卒業(15歳)→高等専門学校入学(5年)→卒業後試験を受ける(20歳)→資格取得→4年以上の実務経験を経て建築士として登録する(24歳)
高校生
高校生になったら、一級建築士の受験資格を得られる指定科目がある大学を受験するために勉強を行いましょう。
高校生が一級建築士になる最短ルートは以下を参考にしてください。
【二級・木造建築士の場合】
高校卒業(18歳)→建築科のある短大(2~3年)→卒業後試験を受ける(20~21歳)→資格取得し、建築士として登録する(20~21歳)
【一級建築士の場合】
高校卒業(18歳)→建築科のある大学(4年)→卒業後試験を受ける(22歳)→2年以上の実務経験を経て建築士として登録する(24歳)
高校卒業(18歳)→建築科のある3年制短期大学(3年)→卒業後試験を受ける(21歳)→3年以上の実務経験を経て建築士として登録する(24歳)
高校卒業(18歳)→建築科のある2年制大学(2年)→卒業後試験を受ける(20歳)→4年以上の実務経験を経て建築士として登録する(24歳)
一級建築士に関しては大学・短期大学どちらに進学しても実務経験の年数によって最短で24歳で建築士になることができます。
社会人・主婦
「社会人になってから目指すのは遅いでしょ?」と諦めかけている人もいると思いますが、そんなことはありません。
建築士の受験年齢は、20歳以上であればいくつでも受けることができるのです。
実際に、社会人になってから勉強を始めた人や、主婦でありながら建築士を目指して勉強している方もいます。
既に建設業で働いている場合、必要な実務経験年数を満たしていれば学歴がなくても二級・木造建築士の受験資格を得ることができます。
ただし、資格取得後も登録要件として7年間の実務経験を積む必要があるので、資格を得るのはかなり先になってしまうため注意が必要です。
もし建設業の経験がなく一から勉強する場合は、大学に通って知識を身に付け、指定科目の単位を取得して受験資格を得る方法をおすすめします。
社会人・主婦の最短ルートは以下を参考にしてください。
【建設業で働いている場合】
7年以上の実務経験を積む→二級・木造建築士の試験を受ける→7年以上の実務経験を積む
二級・木造建築士に登録する→一級建築士の試験を受ける→二級建築士として4年以上の実務経験を経て建築士として登録する
【未経験から学ぶ場合】
建築科のある大学・短期大学に入る(2~4年)→登録要件に応じた実務経験を経て建築士として登録する(2~4年)
大学進学の場合、どの体制の大学を選んでも資格を得るのに最低6年はかかることを覚えておきましょう。
通う学校の選び方

これから通う学校をどうやって選べばいいかわからない人も多いと思います。
ここでは、学校を選ぶポイントを紹介していきます。
学びたいことを学べるか
一番は、学びたいことを学ばせてくれる学科・カリキュラムがあるかどうかです。
建築学科と一口に言っても、その中で学べる内容や範囲は学校によって異なります。
自分が、子供が、どのようなことを学びたいのか一度明確にしてから学校選びを始めましょう。
卒業後に取得できる資格は何か
大学・専門学校進学の目的に「受験資格の獲得」がある場合、卒業後に建築士の受験資格を得られなければ通う意味があまりありません。
受験資格に当てはまる指定科目が受けられるのか、卒業後に受験資格を得られるのかをあらかじめ確認してから選ぶようにしましょう。
通いやすさ
学校への通いやすさも重要ですよね。
しかし、学びたいカリキュラムがある学校が実家から通えない距離にある場合も多いです。
一人暮らしをするとなると、バイトをして生活費を稼がなければいけなくなる可能性も高いので、学校での勉強に支障が出ないかどうかを検討してください。
寮がある場合はその分家賃も安く済むので、学びたいカリキュラムがある学校で比較してみましょう。
費用の相場を知って比較する
大学に進学する場合、入学金が20万円~40万円で、授業料を含む年間費用は100万円程かかるのが相場です。
学校によって変動はありますが、だいたいこのくらいかかることを理解しておきましょう。
奨学金を借りれば家庭の負担が少なくて済みますが、就職後に返還する必要があります。
金利は低いですが「奨学金は借金である」ということを忘れないでください。
しかし、一級建築士になれれば高い給料をもらえるので、奨学金もなんなく返していけると思います。
建築士の年収については、次の項目で紹介します。
気になる建築士の年収は?
せっかく難しい資格をとるので、年収はどのくらいなのか知っておきたいですよね。
一級建築士の平均年収は約700万円です。
日本全体の平均年収は約400万円なので、かなり高い給料をもらえることが分かります。
二級建築士の平均年収は約500万円、木造建築士の平均年収は350~400万円のようです。
資格の合格率が高くなるにつれ給料も上がることが分かります。
建築士に向いている人はどんな人?
建築士になりたい人でも、「自分は建築士に向いているのかな?」「進学したのに途中で無理になったらどうしよう」と不安に思いますよね。
建築士に向いている人の特徴を挙げるので、自分がどのくらい当てはまるかで判断してください。
- 建物が好き
- ものづくりが好き
- デザインするのが好き
- 理系科目が得意
- 責任感がある
- 好奇心旺盛
- 人とのコミュニケーションが苦じゃない
- 臨機応変に対応できる
- 人に喜ばれる仕事がしたい
- 粘り強い
あなたはいくつ当てはまりましたか?
物理や化学などの理系知識は仕事をする上で必要不可欠となるので、そこが欠けていると資格をとること自体が難しいです。
今のうちから勉強して理解を深めておきましょう。
また、コミュニケーション能力も建築士として働くうえで重要です。
クライアントだけでなく現場監督や施工管理技士の方々と話し合いを行い、時にはこちらの意見を突き通す必要も出てくるのでコミュニケーション能力を鍛えなければいけません。
自分が当てはまらないものを把握して、能力を伸ばしていきましょう。
年齢は関係ない!建築士に挑戦しよう
建築士になるのに年齢は関係ありません!
しかし、まず受験資格を得るために大学に通うなど、勉強にかける時間を増やす必要はあるので、ある程度何歳までに何をしていつまでに建築士になるのかの将来像を描いておきましょう。
建築士になって素敵な建物を世の中に残していってください。


コメント