2022年1月から、高所作業をする際はフルハーネスの着用が義務付けられました。
もう知っていて着用している建設業の方も多いとは思いますが、ここでフルハーネスの必要性や注意点などを再確認してもらえればと思います。
フルハーネスとはどんなもの?
 画像出典元:OROSS WORKER
画像出典元:OROSS WORKER
フルハーネスとは、肩から太腿まで複数のベルトで構成された安全帯のことです。
全身にベルトが巻き付くように作られているので、安全帯から体が抜け出てしまうことや腹部・胸部を圧迫するリスクを減らすことができます。
フルハーネスは宙づり状態でも体の重心を頭側に維持できるので、ひっくり返ってしまうことも防いでくれます。
このように、高所での作業員の安全を守ってくれる装備なのです。
胴ベルト型とフルハーネスの違いは、固定部分の違いによる作業員への負担の有無です。
胴ベルトは、ベルトを腰に巻き付けて落下防止する安全帯なので、落下を阻止する際にベルトがずり上がって腹部や胸部を圧迫する危険性や抜け落ちて落下してしまうリスクがあります。
過去には圧迫による死亡例もあります。
フルハーネスの場合、体全体をベルトで覆うことができるので重心が安定し、落下時も体の一点が圧迫されるのを避けることができます。
フルハーネスの義務化はいつから?
フルハーネスの着用は、2022年1月2日から義務化されました。
今まで頻繁に使われていた胴ベルトの使用は一部を除いて禁止され、フルハーネスでの作業が義務付けられています。
なぜ義務化されるのか
建設業では高所の作業が多いこともあり、作業中の死亡事故の原因で「墜落・転落」が最も多いです。
墜落・転落での死亡事故を防止するために、フルハーネスの着用が義務付けられたのです。
フルハーネスは高さ5m以上で着用義務が生じる
6.75mを超える高さ(建設業では5m、柱上作業では2m)の場所で作業行う際は、墜落制止用装置をフルハーネスにしなければいけません。
また、高所作業車でも5mを超えるバスケット内で作業を行う場合はフルハーネスの着用が推奨されています。
ただし、5m以下の高さであれば胴ベルトが許されています。
労働安全衛生法令では、高所からの墜落を防止するために高さ2m以上の場所で作業を行う際は作業床を設け、手すりや囲いを付けることが原則化されています。
安全帯はこのような作業環境を整えられない場合の代替措置なので、フルハーネス着用に気をとられてその他の安全処置を怠らないようにしましょう。
なお、高さが異なる場所を横断して作業する際は、事故のリスクを下げるためにフルハーネスを使用しましょう。
なぜ5mなの?
5m以下の高さでフルハーネスを使うと、万が一落下した際にランヤードが引き出されてベルトに長さが出てしまい、作業員が地面に衝突してしまう恐れがあります。
5m以下ならば落下しても地面に到達するので、すぐに救出することができるということで胴ベルトの使用が許可されているのです。
また、5m以下ならば作業床や手すりを作るなどして安全帯を使わなくても済むような環境を整える方が良いでしょう。
対象者は講習受講義務がある!?
2m以上高所で作業床を設けることが難しい場所に置いて、フルハーネスを着用して行う作業に係る業務に就いている人は、特別教育の受講が義務付けられています。
フルハーネスを含む墜落制止用器具の説明や、労働災害に関する知識など、学科科目に4.5時間、フルハーネスの使用法の確認などの実技科目に1.5時間、計6時間の講習になります。
資格取得にかかる費用は、2023年9月までは10,500円、2023年10月以降は10,505円になります。
ただし、フルハーネスの使用経験があるなどの作業者は一部講習が免除になる場合もあります。
罰則もある
講習を受けずに(無資格で)フルハーネスを着用する作業を行った場合は法令違反となり、
作業を行った者は50万円以下の罰金、作業を行わせた者や企業は6か月以下の懲役または罰金50万円以下の罰則があるので必ず受けるようにしましょう。
ただし、作業床があればフルハーネスの特別教育は受講しなくて良いので覚えておきましょう。
フルハーネス使用時の注意点
フルハーネスを使用する際の注意点をご紹介します。
知って損のないものなのでぜひ覚えておきましょう。
フルハーネスは定期的な交換が必要
フルハーネスは消耗品であり、経年劣化が起こるものです。
使用開始日から3年を目安に交換しましょう。
使用期限内であっても定期的な点検を必ず行い、いつでも安全に使用できるようにしてください。
フルハーネスは新規格のものを使おう
旧規格の安全帯の使用が認められていたのは2022年1月1日までです。
すでに新規格しか使用できなくなっているので認識しておきましょう。
新・旧規格の見分け方
 画像出典元:UNIFORM NET
画像出典元:UNIFORM NET
新規格であれば、製品のどこかに「墜落制止用器具」という文字が入っています。
旧規格であれば、墜落制止用器具という文字が入っていない、もしくは「安全帯」という文字が入っています。
使用前に確認して、新旧を間違わないようにしてください。
視察やパトロールならフルハーネスの特別教育を受ける必要はない
フルハーネスの着用と特別教育は、「2m以上の作業床を設けるのが難しい場所での“作業”」をする場合に必要になります。
視察やパトロールは作業に入らないため、特別教育を受ける必要はないのです。
フルハーネスでも絶対安全ではない
フルハーネスを着用していた場合でも、宙づりの状態が30分以上続くと命の危険があります。
落下時、長時間宙づりになると想定される作業場所においては、うっ血対策ストラップなどの延命処置の装備が求められます。
フルハーネスはたしかに胴ベルトよりは安全性が高いですが、絶対に安全というわけではないことを覚えておいてください。
フルハーネス着用義務のある業務一覧
フルハーネスの着用が必要な業務は何があるでしょうか。
- 鉄骨上での作業
- 足場が設置できない屋根での作業
- 電柱や電信柱での作業
- 鉄塔の組立・変更・解体作業
- チェア型ゴンドラ行う作業
- 天井クレーンホイスト点検業務(ホイストに乗って行うもの)
- 送電線の架線作業
逆に、フルハーネスが必要にならない作業は以下の通りです。
- 足場の手すりを一時的に取り外して行う作業
- パラペット端部、開口部での作業
- 高所作業車で行う作業(バスケット内の高さが6.75mを超得る場合はフルハーネスの着用必須)
- 天井クレーンホイスト点検業務(ガーター歩道上で行うもの)
- デッキ型ゴンドラで行う作業
フルハーネスが必要な業務と必要ない業務があるので、使用前にしっかり確認しておきましょう!
まとめ
フルハーネスは、従業員の安全を守るために重要なものです。
作業現場での安全性は、建物の品質にも関わってきます。
大切な従業員を守るためにも、作業床や手すりをなるべくつけるようにして、安全帯だけでなくその他の要素でも安全な環境を整えてください!
人手不足解消なら建設業向けマッチングサービス「KIZUNA」がおすすめ♪
「人手が足りない」
「仕事をもと増やしたい」
そんなお悩みがある建設業の方、マッチングサービス「KIZUNA」を利用してみてください!
完全審査制で安心してやり取りができますし、シンプルな操作画面で誰でもすぐに操作を覚えることができます♪
無料で登録できるので、ぜひ一度試してみてください。

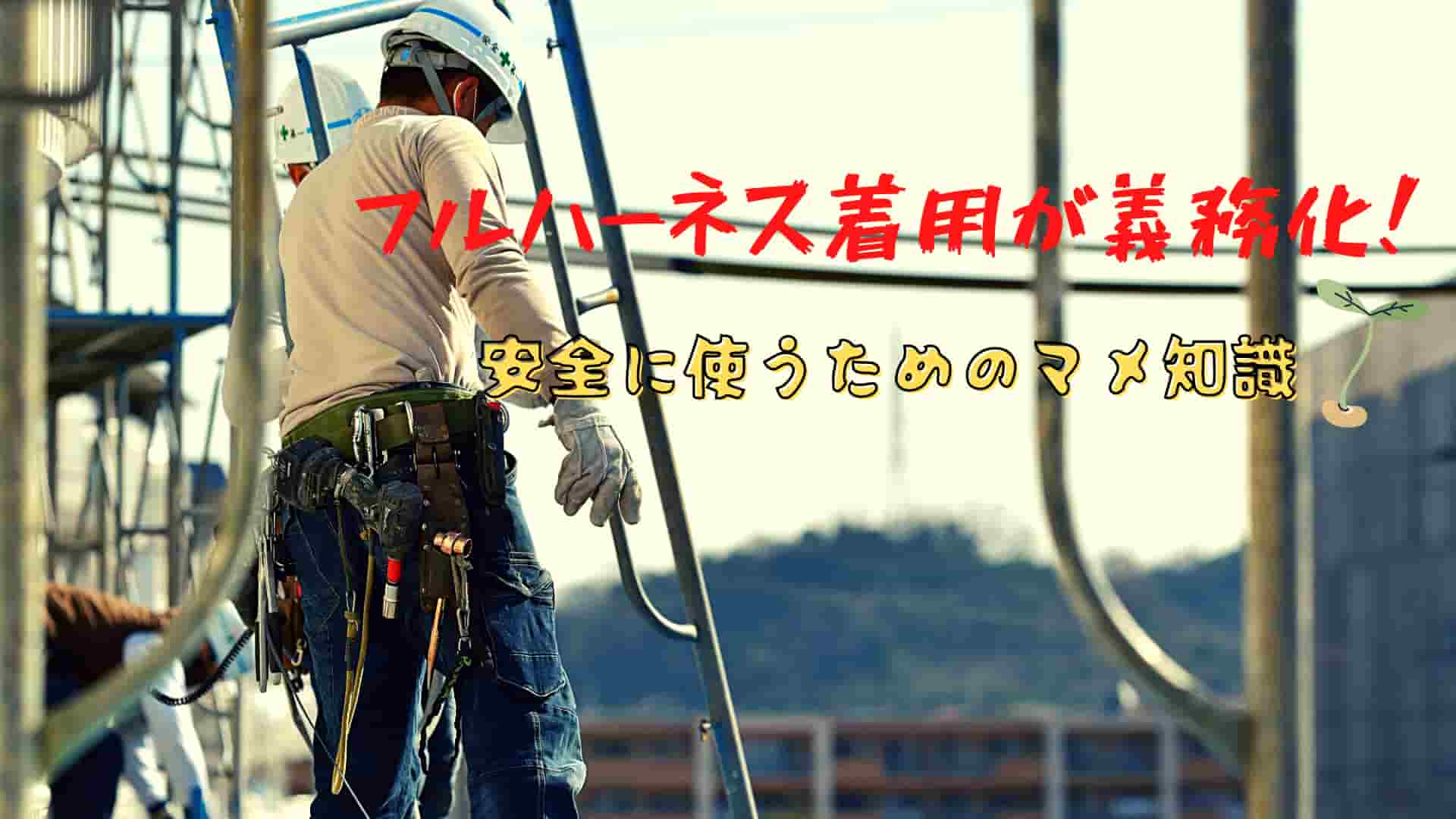
コメント